教育に関するコメント

| 2006/10/31 「単位未履修について」 |
|
最近、学校にまつわる報道がよくされています。研究所のつどいにもそれに関する書き込みがありました。今、教育現場では、混乱が起きていると思われます。生徒のためにと思ってやってきたことが、一部の人のリークによって予想もしなかった事になり、文科省をはじめ政府すらが動くことになったのですから。 |
| 2006/10/26 「単位未履修について」 |
|
富山県から始まって、高校の世界史未履修のことが全国的に波及して各紙面をにぎわしているようですが、こんなこと、教師をしていれば別に不思議でもなんでもない話で、どこでもある程度やってる話です。大阪だけとか、京都だけとか、北海道だけという話じゃなくって、全国レベルでしていることです。コメンテーターや自称専門家なんかは好き勝っていっていますが、別に最近になって目立ったわけじゃないし、それこそずっと前から行われていたんですから、何を今更、えらそうなことを、と思います。 |
| 2006/10/26 「教師の自殺②」 |
|
ここで修正しておきます。先ほど、「スーパーモーニング」という番組で千葉県の自殺した女性教員のこ とが特集されていました。 気になったことが、きつい保護者からの連絡帳への書き込みなど保護者の態度について、コメンテーター から、保護者をたしなむというか、保護者に対して学校とのつながりを絶つようことを短絡的に書くのはど うか、というような内容のことを言ってました。つい最近まで、福岡の事件では、学校は…、教師は…、今 の教育は…、と好き勝っていっていたのに、千葉の事件が起きると急に風向きが保護者の方へをむき出した ように感じます。マスメディアとは勝手なものですね。その時々で身勝手なことをいう。学校で何かあれば 「学校が…」「教師が…」「だから今の教育は…」と責め立てて、教師などが自殺したりすると「保護者の 態度が…」「生徒が…」とその矛先が変わってしまう。とにかく、攻めやすいのを責めているという感じが して見ていて不愉快さを僕はもちます。つい先日まで違うことを言っていたのに、と思うのです。 みなさんはどのように思われますか? |
| 2006/10/25 「教師の自殺」 |
|
千葉市立中学校の男性教諭(50)が自殺した事件が9月にありました。ちょうど、福岡の三輪中学での教員によるいじめでマスメディアで取りざたされていた最中の事でした。僕は、この事件をたまたま朝のワイドショーで知りました。本当に短く報道されていたことを覚えています。最近まで、この男性教諭の自殺に関する詳細な報道をほとんど見ませんでした。報道はされても、記事になって小さく報じられる程度でした。それに対して三輪中学での自殺事件は日を追うごとに大きく報じられるようになり、今でこそほれほど大きく報じられることはなくなりましたが、それでも男性教諭の自殺とは比べものになりませんでした。 |
| 2006/10/18 「いじめ」 |
|
最近、福岡での教師によるいじめを原因とした自殺に関してコメントをしたいと思います。ある地域の一事件と思っていたのですが、その波紋が意外にも多くなってきましたので、少し意見を言っていた方がいいかなあ、と思いまして…。 |
| 2006/10/16 「愛国心は育てるもの?教育するもの?」 |
|
10月14日の土曜日付けの毎日新聞で、《参院予算委 「愛国心」で安倍首相と福島党首が珍問答》と題しての記事が出ていました。ここで少し引用してみます。 |
| 2006/10/10 「今こそ冷静に核や軍事について話し合おう」 |
|
緊急の書き込みです。教育に関することを書こうと、じっくり思案するつもりでしたし、HPの形式を変更したので、慣れるのに時間がかかってました(更新しなかった言い訳っぽいですね(^^;))。 |

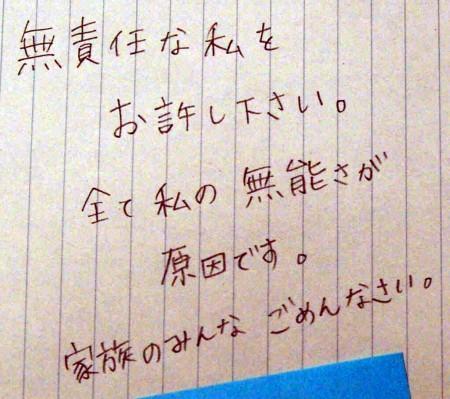 話がそれていきましたが、現在の学校が抱えている問題を一側面で見るのではなく、様々な問題が複合的に重なっていることを認識しておくべきであると言いたいのです。教育再生会議の人たちが新聞などに載せているコメントを見てる限り、「教育委員会をなくそう」というように「○○をかえる」というようなことが多く散見できます。でも、教育というのはそう簡単なものではなく、例えば教育委員会をなくしたから学校現場で起きている問題を解決できるというわけではありません。「教育バウチャー制度」なども持ち上がっていますがそれで問題を解決できるとも思わないし、何故「バウチャー」というとちらかというと経済用語に近い言葉を教育に用いているのか不思議です。単純に、「学校選択自由制」というようにすればいいのです。様々な議論をいちいち取り上げても仕方がありません。ただ、学校現場での問題が教育再生会議などに「教育改革」を任せるのはどこまでその責務を果たせるのか疑問に思います。
話がそれていきましたが、現在の学校が抱えている問題を一側面で見るのではなく、様々な問題が複合的に重なっていることを認識しておくべきであると言いたいのです。教育再生会議の人たちが新聞などに載せているコメントを見てる限り、「教育委員会をなくそう」というように「○○をかえる」というようなことが多く散見できます。でも、教育というのはそう簡単なものではなく、例えば教育委員会をなくしたから学校現場で起きている問題を解決できるというわけではありません。「教育バウチャー制度」なども持ち上がっていますがそれで問題を解決できるとも思わないし、何故「バウチャー」というとちらかというと経済用語に近い言葉を教育に用いているのか不思議です。単純に、「学校選択自由制」というようにすればいいのです。様々な議論をいちいち取り上げても仕方がありません。ただ、学校現場での問題が教育再生会議などに「教育改革」を任せるのはどこまでその責務を果たせるのか疑問に思います。