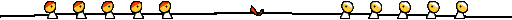教 育 コ ラ ム

| 2025/07/04「隠蔽体質」 |
|
昨今、教師による盗撮やわいせつ行為による逮捕が話題となっている。ネットの記事で見かけない日はないぐらいである。感覚的な話であるが盗撮などで捕まっているのは小学校教師が多いように思える。教師による不祥事で教師全体が厳しい目にさらされている。犯罪者をかばうつもりはないが、教師による盗撮などのわいせつ行為はニュースなどの話題として大きく取り上げられるが、教師の人数に対する割合としてはそれほど多くはない。小学校の教師による犯罪が目立つのはメディアによる宣伝の効果であろう。 |
| 2023/05/07「ずれた働き改革議論」 |
|
最近教師の働き方改革についての記事を目にする機会が多くなったような気がする。この1週間で教師の労働環境に関する記事をネットで見なかった日はないのではないかと思えるぐらいである。それらの記事を読んでいて現場の経験のない記者が記事にするものだから論点がずれている、もしくは本質的な問題点がわかっていないのではないかと思える内容のものが目立っていた。たまたま『京都新聞』が社説を出しいたので参考に掲載する。「教員の勤務実態 長時間労働の根本的解決を」と題された5月7日付16時39分配信の社説である。
以上の記事では「根本的な解決」が学習指導要領の「内容を絞る」か「教員を増やすしか手立てはない」と締めくくっている。他の記事では、教師の業務軽減として部活動を外部委託、地域に移行させるということことが取り上げられていた。これらの内容はある側面においては教師の多忙な業務の軽減に有効ではあるが「根本的な解決」となるか、という点には疑問点が残る。よく指摘される部活から焦点を当てよう。 |
| 2023/04/01「被害者となる子供たち」 |
|
約3年ぶりの記事となる。コロナ禍だから控えていたというわけではなく、単に記事を書く機会を逃していただけ。
3年前の記事で新型コロナウィルス感染症(以後、新型コロナ)のパーフォンマンスについてふれた。新型コロナも旧型コロナと同様に「風邪」であることは指摘していた。新型コロナが取り上げられる前から「風邪」で亡くなる人は存在していた。死亡原因が「風邪」となるか、風邪から誘発される肺炎となるかの違いはあっても亡くなる人はいたのである。それが新型コロナでマス・メディアがバカ騒ぎするのと利権に群がる連中によっていいように振り回されたのがこの3年間である。 |
| 2020/03/15「新型コロナパフォーマンス」 |
|
今年2月末に安倍首相が突然、教育機関に流行している新型コロナへの対応として臨時休校の要請を行った。これにより教育現場ではどのように対応すべきかで混乱が起きた。時期が学年末試験などとかぶっていたために、休校にした場合成績処理をどのようにするのか、教科指導をどのように行うのか、必要な出席日数が足りない場合単位認定はどのように行うのか等々様々な課題に対して急遽対処せざるを得なくなってしまった。おそらく教育現場から言えば迷惑以外のなにものでもなかったと思う。 |
| 2019/11/11「英語試験の延期」 |
|
文部科学相の「身の丈」発言に端を発した大学入試の在り方問題についてどうも話がずれているように思うので、久しぶりに書くことにした。
特に問題として取り上げられていたのが英語の試験である。英語の試験は民間業者の試験を取り入れるもので、それぞれの業者の試験結果が大学入試の判定に利用されるというものであった。そもそもその変更は必要だったのかという議論もあるだろう。以前から僕が訴えていたように昨今の教育行政は単に教育利権でしかないので利権にからんだ入試制度に綻びが出てきたとみるのか、余計な発言で躓いたとみるのか…。 |
| 2018/09/12「働き方改革」 |
|
政府は働き方改革を打ち出し、同一労働同一賃金を企業に求めるようにした。働き方改革を大雑把にまとめると、 |
| 2018/02/25「道徳教材」 |
|
非常勤講師や常勤講師をしている者にとってはソワソワする時期となった。来年度の契約が更新されるのか否かがかかっているからだ。政府が働かせ改革をおしすすめているが、そんなことで末端で働いている者にとっては、働きやすい環境ができあがるものではない。むしろ、姑息な手段がうまれる原因となるだけである。ある一定期間、連続で雇っていた場合は無期限雇用とする、となっても、「連続」でなければいいということで、例えば1年間雇うのではなく3月30日までの有期契約として、1日の空白をつくることで「連続でない」状況をつくりあげている。そのことで、社会保障への加入もいびつになり、1日分加入することができないというケースがある。それを公立学校が率先してするのだからタチが悪い。その手法を私立学校も真似るのである。こうやって負の連鎖が展開されるのである。
この質問に対して府教委の回答は、
とのことであった。こちらは「どのようなお考えなのか」と聞いたことに対して常勤講師を雇う「根拠」を回答してきたのである。国語力に疑問を持たざるを得ない回答をする大阪府教育委員会に対して再度、どのように考えるのか、問い直した。その結果、「この度はご意見をいただき、ありがとうございました。大阪府教育委員会としましては、任用について、今後とも引き続き、法令等を遵守し、適切に行ってまいります」とのことであった。謝意が返ってきたのである。そして、再度道義的に問題のある雇い方についてどのように考えているのかをたずねたが返事が返ってくることはなかった。教育委員会の回答しない態度をどのように捉えるかについては読者に任せたい。 |
| 2017/09/30「政治利用される教育」 |
|
先日、安倍内閣は理由もなく解散総選挙を行うことを公表した。テレビや新聞などでは、自民党と新しく誕生した政党である「希望」との対決、対立構造について報道を行っている。相変わらずの報道の様子であるが、事の本質を誤らずに報道を行ってほしいものである。 |
| 2017/07/09「大学入試としての教採」 |
|
また教採の時期がやってきた。教育現場には、専任以外にも非常勤や常勤講師が教壇に立っている。非常勤は授業が終わればすぐさま帰って行くのが多いが、常勤講師となると拘束時間や仕事内容は専任(教諭)と同じなので遅くまで残って仕事をしている人などもいる。以前にも教採について問題提起をしたが、今回も同じように教採に関して問題提起をしようと思い立った。 |
| 2017/03/20「範を示すべきでは?」 |
|
昨今、就労の在り方について様々な議論が行われ、政府からもいくつかの施策が出されている。最近では、残業時間を「繁忙期の上限月100時間」未満にするように安倍首相が要請したことによって、100時間までなら残業させてもいいのか、と話題となった。また、同じ労働内容である場合は、同一賃金にするようにとの声明も出された。 |
| 2016/12/24「英語教育なんていらん」 |
|
先日、中央教育審議会が学習指導要領の改訂について文科省に答申を出した。その中に、小学5年と6年の英語を「外国語活動」から正式な教科にすることが述べられていたという。高校では、「歴史総合」という教科も出てきているようだが、これについては別の機会に意見を述べたい。 |
| 2016/11/20「本質的な負担軽減を」 |
|
先日、大阪府で週に一日部活動をしない日を設けるということでチョットした話題となった。現場にいる教師は、給与が減らされたボーナスが上がったことの方に気が向いていたのかもしれないが(年収としてそれほどの差が生じていないのではないかと思われる)。
どのような記事があったのか、ネットで拾える限りのものをここで掲載してみよう。
この記事を作成している現時点に於いては、大阪府教育委員会は報道発表資料を公開していないようであるが、それぞれの記事の内容から要点をまとめることができる。まとめると、 |
| 2016/08/28「貧困女子校生」 |
|
毎日様々なニュースが流れる。ちまたでは、いろんな事件などが起こり、情報が垂れ流される。その事件などの結末が報道されることは少ない。ましてや、その背景が詳細に伝えられることも少ない。伝えられるのは、週刊誌や平日の昼間に誰が見てるのかわからないワイドショーぐらいである。その垂れ流された情報の一つで、チョットした話題となっていることがある。NHKがニュース番組で報道した「貧困女子校生」に関してである。僕はその番組を見ていないからどのような内容でどのような映像が流れたのかわからない。ただ、「貧困女子校生」に関する報道のされ方をみていると何となく想像がつくが、それはあくまでも想像の範囲である。 |
| 2016/08/21「うどんとパン」 |
|
今月のはじめに新聞などで、大阪府が「重ね食い」は肥満になりやすいということを発表したと報じた。重ね食いとはあまり耳にしない言葉かもしれないが、簡単に言えば、主食を同時に食べることである。例えば、うどんとご飯、ラーメンとチャーハン、という具合である。ただ、中華料理屋にいけばラーメンセットなど定食でラーメンとチャーハン(焼き飯)がついてくることは珍しくない。少なくとも大阪では珍しくはない。 |
| 2016/08/06「里親の在り方」 |
|
去年のことである、大阪府から里親になりませんか、というような内容のメールが届いた。そのメールを受け取って、うちの子が中学生にもなり、ある程度生活に余裕が出てきたということでかみさんと話し合って里親に応募することとした。応募すると、子ども家庭センター(子家セン)から連絡があり、子家センの職員さんがうちの家計状況や家の内情について事細かく聞かれた。そして、かみなんと僕とでそれぞれ別に個別面接を行い、夫婦での面接も行った。このように書くと面倒だなあ、と思う人もあるかもしれないが、人の子を預ける側としては、信頼できる家庭に預けたいと考えているので、事細かく調べていくということは仕方のない話である。 |
| 2016/07/24「保護者の諦め」 |
|
ネットの記事(『AERA』2016年8月1日号)を読んでいると、プールに日焼け止めを塗るか否かという話題がでていた。内容は、紫外線を浴びることで被害がでることがあるので、日焼け止めを塗らしてほしいという親の思いと水質が悪くなるから塗らせたくないという学校側の思いがそれぞれ書かれていて、単純にどちらが一方的に善か悪かという判断がしづらい内容である。 |
| 2016/07/10「教採再考」 |
|
今年も各都道府県で教員採用試験が実施されたことと思う。大阪でも教員採用試験(以下「教採」)が行われた。ここでは大阪に限って話を進めたいが、大枠としては大阪だけでもないのだが、一応、大阪として限定しておこう。 |
| 2016/06/19「18歳選挙権実施」 |
|
しばらくコラムを書くことをひかえていた。単純に忙しかったのとあまり気乗りしなかったのでコラムは控えていた。それが徒然なるままに書くコラムのいいところである。今日、18歳選挙権の施行に伴い、自称教育専門家がテレビなどで自慰行為的論調を発しているに黙っていられなくなって久しぶりに筆を執った、いやキーボードを打った次第である。ある種、自称専門家連中によって再奮起できたので感謝する。 |
| 2015/09/01「衣服すら奪う」 |
|
半年以上コラムを休んでいた。体調をくずしたというわけではなく、たんにコラムを更新する気になれなかったからで、そのあたりが徒然なるままなコラムでいいだろうと勝手に思っているのである。この半年の間、関大一校の「事前相談」の問題など教育関連の話題は豊富であった。それをいちいち取り上げて、どこかのお姉評論家のように意見をいう気にもなれなかったし、「教育の問題」としてどこまで取り上げるか悩むところであった。
この文章では、本来、常勤講師であっても専任教諭(以後専任)同様にジャージなどの被服を貸与(=支給)されることがわかる。しかし、本年度は申請数と購入単価との関係から申請数の全てを購入数することができなくなった。だから、被服を「支給」するために臨時的任用の職員(=常勤講師、以後常勤)には我慢してもらって、専任には被服を支給するということが読み取れる。必要な人に「支給」するのではなく、専任に支給するために常勤へ「支給」する分を取り上げるという発想である。余談ではあるが、「申請数と購入単価との関係」というのは、単なる発注ミスであると推測する。全体の予算に対して枠内で収まるように発注したが、予算内で収まらなかったということであろう。どこかの国の国立競技場の話に似ているのではないだろうか。規模が小さいので更迭までには発展していないようである。では、先ほどの通知文にある「平成27年3月19日付教委福第1390号」ではどのようなことが書かれているのかというと
としている。「支給」される被服は「着用」の「義務」があることがわかる。そして、申請件数が多かった場合は、「学校ごとに」被服を「調整」する場合があることも記されている。この文章は3月19日付のものである。約5ヶ月後には、各学校ごとに「調整」をする考えはなくなり、常勤へ「支給」をやめることで対応しているのである。「貸与被服の配付及び帳票の印刷等について」と題された通知文は8月17日付である。この通知分を受け取った人は17日以降のことで9月1日になってからのことであった。奇しくも「人権研修」を受けてほとんど時間の経ってない後であった。 |
| 2015/02/27「教育的配慮による通学区域」 |
|
年度末となってきた。年度末となると教育現場では来年度に向けての準備が行われるようになる。そして、傭兵にとっては不安な時期でもある。来年度仕事が継続されるのか否か…。良心的な職場ではなるべく早く継続雇用か否かについて知らせるようにしているが、良心的でない職場ではギリギリまで来年度に関する雇用について何ら知らされない。そんな不明瞭な中、傭兵たちは仕事をこなしているのである。 |
| 2015/01/28「教師を大志を抱け」 |
|
先日、元同僚が職場を去った。理由は何かのオーディションを受けて合格したとか…。辞めた理由は、病気とか家庭のことでというような内容ではなかった。 |
| 2014/12/23「大学入試をかえても…」 |
|
今月22日に中央教育審議会(中教審)が文部大臣に対して、大学入試改革について答申を行った」。その内容は、大学入試をペーパーテストでの選抜から論文や面接を用いた「多面的総合評価」へと変更するというものであった。センター入試の在り方をかえて、「段階別に学力を測り、各大学の個別試験では面接などで「思考力」や「主体性」」をもって判断するものであるという。2021年度から導入を目指すという。中教審とは、自称教育の専門家や学識者といわれる連中がどこかで自分たちが悦にはいるような話し合いをしていると僕は思っているのであるが、連中は現状を把握せず、問題の本質的な部分をみずに判断を下すのである。しかも、偉そうに!! |
| 2014/11/25「平等というのであれば」 |
|
障害をもつ子が通う学校があることをみなさんはご存じだろうか。「特別支援学校」、「支援学校」、「養護学校」と表し方はいろいろある。文科省は「特別支援学校」を用いている(大阪は「特別」をつけずに使うのでここでは「支援学校」と用いる)。 |
| 2014/10/25「大学入試のような教員採用試験」 |
|
今週、大阪府の教員採用試験の最終結果が発表された。今年も職場では採用試験に合格した者が秘かに報告する風景が展開されていた。 |
| 2014/10/07「過剰なハードへの信頼」 |
|
少し時間の経った話だが、大阪府にある二つの高校の廃校計画が教育委員会から発表された。対象校は、大阪府立池田北高等学校と同じく咲洲高等学校である。これに対して、教職員組合は「池田北高校・咲洲高校を守る会」をつくって、撤回を求める署名活動を展開しているようである。僕は、この二校に対して思い入れはないので、廃校に対して賛成・反対の立場ではない。ただ、腑に落ちない点があるので、今回、コラムで取り上げることにした。
新聞記事だけでなく、TVのニュース報道でも沈痛な面持ちで記者会見に挑む校長二人の姿が印象的であった。記事と校長二人の映像を見ながら違和感をおぼえた。それは、府教委は無駄ではない予算をつぎ込んで人事改革?のようなことをして、民間人校長など公募校長を登用してきた。面接などでも自分たちの目だけでなく、金を使って外部の人間に頼んで人物物評価をするぐらいの手の入れようである。そのような「改革」を人事面でして、登用した校長を当てた結果、「定員割れ」という理由で廃校にするのである。廃校にならないように最善を尽くした結果の結論であろうか。そうならないために民間人校長を登用してきたのではないだろうか。 |
| 2014/09/21「過剰なハードへの信頼」 |
|
2年ほど前だったか、大阪の府立学校ではパソコンの端末をどこかにある中枢のコンピューター(以後サーバーとよぶ)で一括に管理を行うようになった。現場には、富士通のスタッフが来て、いかに「便利」になるかということを力説していた。その説明を聞いていた教師からはほとんど質問らしい質問がでずに終わった。たまたまその職場だったから質問がでなかったのか、わからないがスタッフが「便利」なになるという説明によくわからないまま、フーンという感じで説明会は終わった。その時、僕は「便利」になるはずがないと思っていた。現状でもそれほど不便を感じていなかった。なんで「便利」を強調するのであろうか?パソコンの電源を切るだけでも面倒くさい作業をしなくてはならず、単純にシャットダウンを押して終わりとならないのである。何がここまでネットワークの一括管理にこだわったのだろうかと考えてみた。 |
| 2014/08/05「自ら人材を集めよう」 |
|
今年も大阪府では公立学校の校長を公募した。内部からと外部から採用するので、全ての校長が「民間」校長というわけではない。しかし、内部と外部では扱いが異なる。一方は期限付きでないのに対して一方は期限付きである。同じ職種であるにもかかわらず、管理職も現場同様に正規職員と契約職員とわかれるのである。一応、教師であるので、職員と言ってしまっていいのかどうかわからないが、現場の教師同様に異なっているのである。そして、その期限付校長が昨年から話題となっているように問題を起こしているのであるが、期限付校長だけがもんだいであろうか。 |
| 2014/07/03「なじめないのはハードの問題ではない」 |
|
今日付の時事通信で「幼児教育無償化を」と題して、「小中一貫教育学校の制度創設」や「質の高い教育」で「小学校への移行を円滑にする」ための提言が教育再生実行会議でなされたと報じていた。一見、「質の高い教育」を施すことによって、小学校に於ける「集団生活になじめない」状況を改善し、さらに中学校での「集団生活になじめない」子達にも手厚い教育が施されるかのようにみえる。本当にこんな自称専門家達の言い分によって問題が解決できるのであろうか。 |
| 2014/06/08「5歳からの義務教育化」 |
|
現在の教育制度に対して、「何か」をしようとしている文科省は、教育再生実行会議の提言を受けて、5歳からの義務教育化の検討をはじめたという。6月4日付けの『産経新聞』Web板では、「5歳児から義務教育 文科省方針、小中一貫校を制度化」と題してそのことを報じている。 |
| 2014/05/29「大阪府民間人校長説明会」 |
|
昨夜、大阪府民間人校長説明会に参加してきた。場所は新大阪駅の近くにあるグロービス経営大学院大阪校の一室であった。19時からの開始であった。会場には、満席とまではいかないまでも、各テーブルが埋まるぐらいの人が参加していた。流れをおおざっぱに分けると、①松井知事のビデオメッセージ、②校長の募集要項の説明、③パネルディスカッションの3部構成となっていた。
教育委員と司会以外は、現校長である。三国丘と岬高校の校長以外は「民間」から選ばれた校長である。司会が用意したシナリオ通りに事を進めていく。それぞれテーマによって各校長、教育委員に話を振り、各々が考えや体験を語っていた。学校文化を知らない者からすると普段しることがない校長の仕事内容や教師達の様子を聞くことができておもしろかったのではないかと思う。さらに時間を設けて「質問」をパネラーにすることができた。その質問はあらかじめ用意されているものではないので、各々が言葉を選びつつ慎重に答えていた姿が印象的であった。 |
| 2014/04/30「無責任教育の結果」 |
|
4月29日付のWeb版『産経』で、「「先生は何もでけへん」現場の萎縮逆手、生徒の挑発エスカレート 指導に踏み込めない学校の実態」と題された記事がでていた。内容を簡単に要約すると、市立桜宮高校での「体罰」による自殺事件で、生徒達が「増長」し、「挑発」行為が行われ、それに対して教師が「萎縮」しているのだそうだ。その結果、教育現場に於いて一種の混乱と言うべきなのか、事態の収拾がつきにくい状態になっているという。詳しくは、ここをみてもらいたい。自分たちが事件を煽っておきながら、今度は教育現場が困っていると無責任にも記事を掲載してくれているマス・メディアがある。 |
| 2014/04/22「関西の独立精神」 |
|
先日来より、『毎日新聞』を読んでいるとちょくちょく目にする記事がある。その記事の内容は、教員間である程度の人事を行っているという内容のものである。僕は、大阪の学校でしか勤めたことはないが、たいていは教師間である程度の人事を行っている。このある程度というのがくせ者であるが、基本的には人事権は校長が握っている。公立となると教育委員会になると思うが、実質的には校内に於ける人事は校長が行っている。それは建前であって、実質的には教師間である程度調整を行っている。何故か、そうしないと学校の場合、現場がうまく動かないからである。
報道されている記事の中で気になる言葉は、「教員間の選挙」という表現である。クラス担任や学年所属に関しては、「選挙」というよりはそれぞれが話し合って、現場レベルで調整していると言った方が適切ではないかと思う。首席や主事を「選挙」で選んでいることもあるだろう。「選挙」で決めていると言えば決めているのであろうが、選挙で選ばれた教師を現場が推薦していると考える方がいい。あくまでもその推薦を受けて校長が承認するのである。
と報じている。確かに、教師間から選ばれた「ボス的な教員」の性質によって職場が良くも悪くもなる。ボス的な教師の横暴が昔のようにまかり通るような現場ではないし、ボス的な位置になるには相応の人望等が必要となってくる。決して、『坊ちゃん』の赤シャツのような教師が選ばれることはないだろう。むしろ、校長の独りよがりの人事によって赤シャツを生み出す可能性は高い。 |
| 2014/01/20「ゆとりの二重被害」 |
|
あまり意味があると思えないセンター入試が終了した。今回のセンター入試に関して気になる記事があった。うちで購読している『毎日新聞』では、今回の試験に挑むのは最後の「ゆとり教育」の世代であるというのである。来年からは「脱ゆとり教育」世代と競争することになって、不利になるため、今年の試験にかけるという内容のことが書かれていた。その記事自体はどこに行ったのやらわからない。ネットで調べると、同じような内容のことが『読売新聞』のWeb版や『埼玉新聞』Web版でも取り上げられていたので、気になる人は「ゆとり、センター」と検索すれば見つけることができるだろう。 |
| 2014/01/07「生徒の責任」 |
|
以前、大阪の高校で体罰を受けていた生徒が自殺したという事件があった。同質の話ではないが、大津ではいじめを苦にして自殺した生徒のことで学校や教育委員会が事象を認めない、又は隠蔽があったということで学校教育に対して強い批判が浴びせられた。 |
| 2013/12/28「無責任体質」 |
|
いきなりで申し訳ないが、『毎日新聞』Web版に掲載された記事をみてもらおう。
この記事の配信は、12月26日22時53分である。この記事を僕が目にしたのは、翌日の『毎日新聞』朝刊であった。タイミングがいいのか悪いのかわからないが、たまたま「民間人校長だけではない」と題した記事を書いた翌日のことであった。 |
| 2013/12/27「民間人校長だけではない」 |
|
流行語のようにその時の流行にのってコラムを書くことを控えていたあまのじゃくな僕である。年末ということもあり、記事を書いてみた。 |
| 2013/10/20「修学旅行先」 |
|
いつだったか、外国人記者が東電に対して「日本人の忘れやすい性質を利用して云々」と情報を小出しにすることを批判していた。その指摘は正しいのだろう。日本人は自分に関係ないこと、関係があっても時間と共に忘れてしまい、都合の悪いことはなかったことにする性質を持っているのかもしれない。 |
| 2013/09/29「給食の安全」 |
|
2011年3月11日に東北地方で大地震が起きた。地震による津波の被害は予想し得ないような被害をもたらした。しかし、津波以上に深刻だったのが、福島の原発事故である。事故という表現は事の大きさを矮小化しかねないので、僕は福島メルトダウンと言った方が事の本質に近いのではないかと思っているので、そう表現する。ここでは、原発事故の詳細について専門的なことを述べる場ではないので、メルトダウンが云々と言うつもりはない。 |
| 2013/09/17「責任をもつということ」 |
|
昨今、大阪府では民間人校長を中心に不祥事が目立っている。民間人から校長に抜擢することが問題ではない。問題は、その抜擢の仕方であり、そのシステムの運用にこそ問題があると考えている。 |
| 2013/08/22「不合格は不合格」 |
|
いつだったか、大阪市の人事で教頭の数が足りなくて、不合格となっていた人間を合格とした話がニュースでながれていた。管理職のなり手がいないというのだそうだ。ニュースでは、なり手がいない、人手不足であることを伝えていた。新聞でもこの内容は書かれていたが、僕の知る限り適材適所について議論をするところはなかった。大阪では、教員採用試験の1次の結果が発表されたこともあり、適材について所見を述べてみたい。 |
| 2013/06/22「捨てるぐらいなら」 |
|
昨日、ネット上で以下のような記事がでた。『産経新聞』Web版6月22日付18時20分配信の記事だ。全文をそのまま掲載する。
この記事の締めくくりとして、「まだ食べられるものを杓子定規に規則で捨ててしまうのはどうか-といった意見もあるだろうが、役得的に余った給食を食べていた調理員の行為は、とてもほめられたものではないだろう」とある。僕も同意見だ。公務員とは考える能力よりも規則を守る能力を優先する傾向がある。「残ったもの」を捨てることはもったいないから持って帰ったり、食べたりすることは処罰の対象になる。このことは西宮市だけではないだろう。規則だからといって、まだ食べられるものを「捨てる」行為は如何であろうか?日本は平和で餓死者が出ることは稀である。食べ物がなくて飢えている人たちの目には、規則だから食べられるものを「捨てる」行為はどのように写るだろうか。 |
| 2013/05/01「安定した「教師」」 |
|
久しぶりに筆を執る。こんな言い方は古いだろう。キーをたたくと言うべきだろう。約1年ほどホームページを更新してこなかった。その理由は、いくつかあるが単純に忙しかったからであることと少し距離を置いて現状を見てみたかったからである。また、不毛な活動を再開したい。 |
| 2012/05/28「条件付き公募」 |
|
今日、大阪府教育委員会のHPで「大阪府立学校校長公募」のお知らせが掲載されていた。民間人からの校長採用は今まであったが、橋下さん率いる維新の力によって、公立の学校長を今までの民間人から校長を採用する方式を改めて、校長職を「公募制」としたのである。条例が成立してからしばらくたってどのような内容で募集のするのか期待していた。今までとの「違い」を強調していたのであるから、斬新な内容で訴えてくるのであろうと。 |
| 2012/04/26「原因のすり替え」 |
|
先日、京都亀岡で通学途中の児童の列に軽自動車が突っ込み10人ほどの死傷者を出した事件が報道されていた。まだ、小学2年生の子がなくなり、登校に付き添っていた妊婦の保護者までが死亡した。胎児も助からなかったという。この事件は、無免許運転の未成年者が、居眠り運転をした結果起きた事故だった。 |
| 2012/03/27「されてイヤなことはしない」 |
|
大阪府教育基本条例についてコメントをしてきた。今回は今まで教育基本条例に関して見聞きしてきてどうしても一点理解し難いことがあるので、意見をいただくことを目的としつつ、コメントを書くことにする。 |
| 2012/02/27「義務教育について議論しよう」 |
|
2月22日だっただろうか、前社長である橋下さんが小中学校の「留年」について言及したことで、何かと「留年制についてどう思うか?」と聞かれることがあった。もちろん職場でも少々話題となっていた。
上記の文は『毎日新聞』Web版2月22日の午前に配信されたものである。橋下さんのこの発言は、「尾木ママ」の提言にのったものと報道する祭り上げメディアも存在したが、「留年」を主張する教育関係者はそれほど珍しくない。少なくとも僕もその主張をするものであり、以前、コラムでも取り上げたことがある。
この記事では、留年を「させる」ことによって①コストがかかる、②教育的効果はない、③生徒間格差が拡大、④留年した者が悪行をするなど負のイメージを彷彿とさせる言葉がてんこ盛りとなっていた。 |
| 2012/02/06「内田樹さんのブログ」 |
|
教育とはずれた話となるが、今回、神戸女学院大学の教授をされていた内田樹さんのブログをリンクさせてもらったことを記事にする。内田さんとは面識があり、よく話などをする仲だからリンクすることに快諾してもらった、というわけではない。今まで、僕が内田さんのブログをみていて、リンクしちゃおう!と思ったから勝手にリンクしたのである。 |
| 2012/01/22「調書人事」 |
|
久しぶりにコラムを書く。ずっと「忙しい」ことを理由に書くことをやめていた。僕の私的なコラムと化しているので、長期間の空白というのもいいかと思い、怠けているとあっという間に2ヶ月何もせずに過ぎてしまった。自身の怠慢に反省である。この間、何もしてなかったのか、というとそうでもなく維新の会から提出され、知事提案になろうとしている「大阪府教育基本条例」ついて考えていた。現場の人間や自称専門家は、この条例について「とんでもないもの」として扱っている。弁護士の一部も「大阪府教育基本条例(案)に反対する意見書」なるものを出して「批判」している。この件に関しては、延期してここでは述べない。僕は、この条例を読み返すうちに教育を「ダメ」にする内容なのか疑問に思っている。だからといって、とても良い条例であるとは言わないが、条例が提案されることの真意が何なのか考えているうちに時間が経ってしまった。未だにその答えにはしっくりいっていないので、ゆっくり考えることにする。 |
| 2011/11/14「戻ってはこない」 |
|
今日、ネットのニュースを見ていると「津波で園児死亡 遺族が宮城・山元町を提訴」と題された記事を見つけた。記事内容は以下の通りである。
こういう訴えには珍しく行政側は一部であっても責任を認めているという。事件や事故が起きた時に知らん顔する企業などとは違うようだ。災害が起こってしばらくすると、施設や行政相手に裁判を起こすニュースを目にすることがある。明らかに施設や行政に落ち度がある場合ならともかく、その判断がしにくい場合もある。どこかのビデオ店の放火事件のように経営者側の恣意的な避難経路の妨害などとは異なる。 |
| 2011/10/31「「貧困の連鎖」防止へ学習支援 」 |
|
先日、Mixiの日記に同じ題でコメントを記載した。企業のあり方、保護者や家庭のありかたが問われなければならないのに、「学習支援」と問題の本質部分をすり替えて、金で解決しようとする政府のあり方に対して私見を述べた。以下は、その再掲載と思っていただいて結構である。
貧困が貧困を呼ぶことに対して完全否定するわけではない。負の連鎖が起きやすいのは理解しているが、負の連鎖を断ち切って、そこから這い上がってくる人間もいる。まれにいるからこそ、映画やドラマ、小説のネタにもなるのだ。そして、まれに成功者がいるからこそ、昔から○○さんのようにと親は「蛙の子は蛙」にならないことを信じて子供に叱咤激励してきたのである。努力と運によって成功する者もいるのが人の社会である。このことは、最近の話ではなく、大昔から存在する話である。成功する人間、失敗する人間、どっちつかずの人間、それらが混在して社会を形成している。努力と運などによって人はそこから這い出たりする。それを何でも平等主義のわからずやたちが騒いで、「貧困の連鎖」を断ち切るため人公的資金を投入することを検討しだした。貧乏人と子供を見方につけた施策だから、これに反対する者は人でなし扱いされるので、面と向かって反対の声をあげる人は少ない。貧乏人は常に正義でもなんでもない。ただ、数が多いだけである。そのうちの一人が僕であるが。 |
| 2011/10/14「カンニング」 |
|
たまたま職場で「試験」について話題がでた。年配の教師は、定期考査における試験監督が自分にはあっていなかったと話してくれた。そして、よく本を持って行って試験中読んでいたという。これを聞いたもう一人の教師が、今の公立高校でそんなことをしたら大変なことになると言っていた。 |
| 2011/09/06「大阪府教育基本条例」 |
|
8月は暑いのでHPの更新は控えていました。単純に怠けていたという見方もあるが、活動を休止している間に教育に関する事象がいろいろとあった。その中でも際だったのが、橋下さんが所属するというか代表の大阪維新の会が打ち出している「大阪府教育基本条例」に関してである。この条例については大枠についていろいろと報道などされているが、その中身となるとなかなかわからない。なぜか?条例案そのものが公開されていないからである。大阪府教育基本条例には情報の開示が明記されているが、その条例の「案」は開示されていないようである。少なくとも、僕が調べた限り、大阪維新の会のHPでは公開されていなかった。このようなことは「君が代起立斉唱条例」の時も同じで、議論というか話題沸騰にマスメ・ディアがしているときも、その内容の全容が明示されていなかった。
|
| 2011/07/16「青田には熟した物はない」 |
|
今日あたりから大阪府では教員採用試験が始まったい。いろんな想いをもって受験している人がいるのだろう。
今年の教員採用からは一部北摂地域で独自の採用をすることになった。自治体が独自に教員を採用するのだが、形式は府の教員採用試験に乗っかっているので、「独自」とはとうていいえる代物ではないだろう。その自治体が「優秀な教師」を確保するために、特に新卒者に向けて説明会なども含めて、あの手この手を使っているらしい。なぜ、新卒者なのかよくわからない。「優秀な教師」を確保するのであれば、ヘッドハンティングをするのが常識だと思っている僕は、教育委員会から見ると非常識なのかもしれない。 |
| 2011/06/07「君が代起立斉唱条例の内容」 |
|
全国初となる「君が代起立斉唱条例」が6月3日に大阪府議会で可決された。以前、このコラムでも「強制」することの是非とりも、民主主義国家における個人をたたえる「君が代」の問題について論じた。橋下さんが府議会に提出した「君が代起立斉唱条例」の中身は新聞やTVでは「強制」のみが強調され、その中身が伝えられることがほとんどなかったので、ここにその条例の中身を記載する。 この中身を読んでいただければ、この条例が十分に吟味されず、とにかく公務員(特に教師)を公の場で起立斉唱させる為の「根拠」をつくろうとした様を見て取れる。 橋下知事のことだからスピード感をもって必要なことを決めたと言えば聞こえはいいが、その内容が十分であるか否かを審査するのが議会であり、橋下派だからといって無条件に条例などを吟味せずに仮設させてしまうのは、議員としての「責務」を放棄している感がある。それではナチとなんらかわらない。ナチは突然現れたのではなく、「市民」から「選挙」という手段によって選ばれ台頭し勢力をもったことを義務教育によって「学力」をつけた「市民」なら知っているはずである。その危険性は留意する必要がある。 話がそれた。この条例に掲げられている目的には、国旗掲揚や君が代斉唱によって、①「府民、とりわけ次世代を担う子どもが伝統と文化を尊重し」、②「それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資する」ことになり、③「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養」い、④「府立学校及び府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図ること」が目的となっている。 国旗掲揚と君が代斉唱を行うことによって①「府民、とりわけ次世代を担う子どもが伝統と文化を尊重」できるか否かは不明であるし、②「それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識」がそんなことで「高揚」するはずもなく、国旗掲揚と君が代斉唱が③「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養」える根拠がよくわからない。明確なのは、④教職員に対して「服務規律の厳格化」の徹底を狙っていることぐらいである。 どこでも言えることだが、規則として強制的に何かをさせようとする場合、大義名分が必要である。「公務員なのだから当たり前」ではすまされる話ではないようで、強制させる為の大義名分が①~③にあたり、本音は④である。教職員に対する「服務規律の厳格化」をさせる為のわかりにくい非論理的な口実がつけられている。 簡単に言えば、イベントで管理職の指示・指導に従わない職員(教師)がいて、その処罰の為の根拠があやふやだから、不良職員を一掃する為に君が代起立斉唱条例が制定されたのである。こういう騒動に巻き込まれる人間はとても迷惑な話である。採用するときに人間を「見抜ける」と豪語する採用官の 責任もついでに明記してみては如何だろう。無責任かつ丸投げ式の採用が見直されるかもしれない。 |
| 2011/06/05「君が代起立斉唱条例」 |
|
5月上旬に大阪府知事の橋下さんが「君が代起立斉唱条例」の作成を指示して、5月25日に提出されたという。そして、6月3日に大阪府議会で可決された。新聞などでは全国初として一面を飾っていた。ネットでも君が代を「強制」することによる賛否両論がなされている。公務員であるから国歌国旗に起立などするのは当たり前ではないか、憲法に定める思想・信条の自由に反する(第19条)など様々な意見が出ている。 |
| 2011/05/12「家庭訪問」 |
|
5月の上旬が終わろうとする頃、主に小中学校では家庭訪問が行われる。家庭訪問をする意義はどこにあるのかと問う人もいるだろう。共働きや片親で仕事を持っていれば、平日の昼間から夕方頃に担任がやってくる家庭訪問は、わざわざ仕事を休んだり、早引きしなくてはならないからだ。家庭訪問をしていてあからさまに迷惑であるということをいわれたという話は聞かない。むしろ長時間拘束されて担任が閉口することを耳にする機会が多い。
ことである。これだけが目的ではない。むしろ家庭を観察することが大きな目的である。児童や生徒の家にいって、その家の中の様子を知ることによって教師はある種の空気を感じ取るのである。この家は意外としっかりしている、ムラがあるのはこういうところからか、子供の落ち着きのなさはこういう環境からなのか、などなどいろいろ感じ取るところはあるだろう。しっかりしていそうで、家を見る限りそうでもないということもある。家をみることで子供が生活する環境を知ることができるのである。家庭環境の観察は重要であると僕は思っている。そのことで子供姿を重ねて妙に納得できることが多々ある。 |
| 2011/04/11「非効率的なもの」 |
|
2011年度が始まった。入学式があり、始業式があり、気がつくと4月も三分の一が過ぎ去っていた。年齢を重ねたからなのか、月日の経つのが早いとつくづく感じるようになった。子供たちはどのようにとらえているのだろうか。人生17年や18年ぐらいの子の一日と35年も過ぎた人間の一日とでは、その一日の感覚は違うのだろうか。自分が高校生だったころのことを思い返そうと思っても今ではそんな感覚を思い出すことができない。ただ、新年度に入ってどんなクラスでどんな1年が始まるのだろうかと漠然と考えていたに過ぎなかったのだろう。 |
| 2011/03/27「甘い生活を保持したいと言えばいいのに」 |
|
3月14日に大阪府議会教育常任委員会は、2011年度の私立小中学校への運営補助金(私学助成)を約11億円削減する方針に対して撤回を求めるように全会一致で決めたとの報道がなされた。この報道は一見、私立学校に通う小中学生の家庭にとって「良い」施策のように思える。しかも、見出しに「小中学校の私学助成削減撤回を 教育の質低下懸念」(『朝日新聞』)とでると、橋下知事が行おうとしている小中学校への私学助成削減が、教育の質の低下を招くように思われる。しかし、助成金が削減されることが本当に教育の質の低下を招くのだろうか?さらにご親切に府議会教育常任委員会で「私学経営への悪影響」を考えてくれているが、そのことも本当なのか考えてみたい。 |
| 2011/03/04「カンニング行為で騒ぐ愚行」 |
|
「本屋になる前、一時東京帝国大学の事務員だったが、あるき学年末試験の監督を命じられたのに、人を疑うそぶりを見せるのはいやだなどと教卓によりかかって思い悩んでいるうちに、いびきをかいて寝こんでしまったので、なかなか豪傑だと学生の評判が一遍によくなった。」 |
| 2011/02/27「英語は道具」 |
|
新聞をみていると英語教育に関する記事をちらほらとみることがある。大阪に住んでいるので、おそらく大阪府教委というか橋下さんの影響もあるのだろう。大阪は英語教育にご熱心なようなので、英語教育について行われたシンポジウムの記事や英語教育を進める私立学校の取組、さらには小学校での取組についての記事に出くわすことがあった。 |
| 2011/02/02「市民の声による学校いびり」 |
|
公立学校にいると「府民感情」と「府民の目」なる言葉を耳にすることがある。「市民の意見」として学校や教育委員会に直接意見が寄せられているというし、場合によっては議員が「市民の声」として教育委員会に意見を言っていることもあるらしい。私立学校にいたときにはほとんど聞くことのなかった言葉である。私立学校では「保護者」が使われることの方が多かったように思う。 |
| 2011/01/17「受験と震災」 |
|
新聞やテレビで今年も1月17日となると阪神淡路大震災についての話題が出ていた。こういう言い方をすると噴飯する人も出てくるが、正直にいうと「またか」という気になる。震災だけではないがこういった内容の話は批判したり、少しでも否定的な話をすると人でなしのように言われるが、僕は感情的な封じ方には賛成できない。話がそれた。いきなりそれたので元に戻そう。 |
| 2011/01/05「受験生年末年始返上」 |
|
2011年が始まった。当然と言えば当然であり、来年になれば当然のごとく2012年が巡ってくる。人類が滅ばない限り……。しかし、来年が平成24年になるかどうかはわからない。それは天皇さんの体調次第だろう。 |
| 2010/12/21「進化による退化か」 |
|
今月16日に文科省が小学5年生と中学2年生を対象とした10年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査を発表した。この発表内容は当研究所にも送られてきていたので、16日の段階で知ることができていた。気になったのは、この結果をどのように扱うのであろうかと思って、様子を見ていた。各地域で様々なことが新聞などで書かれていたが、当研究所がある大阪を例にしてみてみよう。
多少長かったが記事を全文引用した。ネットの記事はいつ内容が変わるかわからないし、いつまで情報が保存されているのかわからないので、全文引用することにした。 |
| 2010/12/08「教員養成課程で養成できない場合」 |
|
12月8日付で文科省が「国立の教員養成大学・学部(教員養成課程)の平成22年3月卒業者の就職状況について」と題した報告をした。誰でもみることのできる報道発表資料である。これには、「小、中、高等学校等の教員養成を目的とする国立の教員養成大学・学部卒業者(45大学・学部)の教員養成課程の就職状況」が記されている。どこに誰がどれくらい就職したというような具体的なものではないが、今年の3月に卒業した学生の大まかな進路について興味深い数字を挙げているので、それを材料にして話を進めたい。 |
| 2010/11/26「攻撃よりは乞食化の議論を」 |
|
先日、北朝鮮による韓国領への攻撃が行われたとの報道があった。民間人も犠牲になったとのことで国のエゴに巻き込まれた気の毒であったと思う。攻撃を加えた島がどちらに属しているのかについて論じつるつもりは毛頭ない。自分の領土と主張する北朝鮮には自分の領土に攻撃を加える不自然さ、韓国には自国民を守るために存在する軍隊を持っているにもかかわらず、自国民が殺されて形式的な行動にとどまる理不尽さに対して考えるところはあるが、ここではそんな政治的な話には踏み込む気がないのでここらあたりでこの話はやめておく。もう少しつきあってもらえるなら、軍隊が自国民を守るために存在すると言いながら、自国民に銃口を向けた歴史と自国民を守ろうとした歴史とではどちらが多いのか、今回の事件でも考えさせられた。これを機に北朝鮮が、韓国が、アメリカが、日本の立場は云々と議論する前に「軍隊」の存在について議論がでたらと期待する。 |
| 2010/11/11「エリート教育」 |
|
大阪府では、橋下知事が韓国で学校見学をしてきて触発されたからなのか、エリート教育のために教員を海外に研究派遣するとの記事が出ていた。大阪以外でもエリート教育に関しての話を聞く機会があった。エリート教育について今回は論じてみたい。 |
| 2010/10/26「大阪府教員採用試験結果」 |
|
今日、大阪府教員採用試験の発表があった。2次試験の結果で、これに合格していれば事実上これで公立学校の教諭になれるのである。新卒の人、講師の人、民間会社の人、様々な人が教員採用試験に挑んだことであろう。この教員採用試験については以前にもコラムで述べた。簡単にまとめて言えば、教員採用試験の見直しから教育改革を推し進めてみては如何という内容のものであった。今日、教員採用試験の結果がでて、やっぱり教員採用試験の見直しが少なくとも大阪に於ける教育改革の一端となると改めて感じた。 |
| 2010/10/13「今年も教育産業ご苦労さん」 |
|
10月8日付けで文科省は、「平成23年度全国学力・学習状況調査を実施するための準備委託事業に関する委託先機関の決定等について」と長ったらしい題の発表を行った。全国学力テストについては以前よりここで取り上げているので、その是非については改めて論じるつもりはない。今年もこの時季がやってきたのかとのおもいで、今年も取り上げることとした。 |
| 2010/09/23「芝生の管理」 |
|
9月16日に文科省から「教員免許更新制について」という知らせが届いた。まず、「教員免許更新制について、文部科学省としての現時点における考え方をお知らせします」とあり、以下に「教員免許更新制について、文部科学省としての現時点における考え方は別紙のとおりです。なお、別紙については、関係機関にお知らせしました」と続いていた。そして、その別紙は以下の通りであった。
以前から出ている通達文と大きな違いはない。とりあえず、教員免許更新制は現行通りに続いています、と知らせたいのであろう。特に教育現場では、この悪政がなくなることに期待しており、民主党政権はこの制度の改めをうたっていたので、その言葉を信じてすでにこの制度がなくなっていると思っている教師がいると大変だから知らせているのだろう。 |
| 2010/09/13「芝生の管理」 |
|
先日、自治会の会合に出ていて近所にある小学校の芝生についての話がでた。今年は、猛暑で芝のつき具合が悪いという。そんな話をしつつある人が「今年はすでに3回も芝刈りしたで」と言っていた。根付きが悪いところもあるが、そうでないところはすくすくと育って伸びているという。そして、その芝を枯らさないように校庭に移植された芝に水やりをいろんな人が関わってしているとも言っていた。 |
| 2010/08/30「なんでも対応できるわけがない」 |
|
8月ももう終わろうとしている。9月になると学校が始まるところがあるのではないだろうか。しかし、2学期を8月の下旬にはじめるところも相応にでてきていると耳にすることも多くなった。大阪府下のいくつかの市では8月26日から2学期をはじめているところがあるという。夏休みももうおわっているところもあるのである。
アメリカらしい考えと言えば考え方である。日本ではこんな考え方はできないだろう。僕の知っているカウンセラーの人から聞いた話だが、以前、日本にアメリカで有名なカウンセラーが来て活動をしたことがあったらしい。しかし、その人は日本の環境に合わずにしばらくしてアメリカに帰ったという。その環境とは考え方であったという。先にも挙げたように何でもかんでもフォローしようというのが日本の考え方であり、できないものはできないと考えることはない。自虐的になろうとも責任の大きさをふくらませて活動するのが、日本の在り方のようだ。さて、これを教育に置き換えた場合どのようになるだろうか。 |
| 2010/08/11「テストと評価」 |
|
今月の頭だったろうか、学力テストの結果などを報じる記事がちらほら目にすることがあった。未だに学力テストについては教育産業利権について論じられることなく、テストの実施方法やその結果に関して云々論じられることが多い。ここで敢えて教育産業利権について話をすることはやめて、少し違ったことをここで紹介したいと思う。
|
| 2010/07/30「体罰問答」 |
|
夏休みに入って10日ほどが経とうとしている。学校の先生は夏休みは学校が休みなんだから遊んで暮らしているのだろう、楽だろう、と思われがちだがそうではない。夏休みに入れば処理しなくてはならない書類などがありそれを処理したり、よくわからない「研修」なるものは続出するのである。この研修の在り方には思うところがなくはないが、ここではその是非については触れないでおこう。今回取り上げるのは、いろいろ行われる研修の中でも「人権」をテーマとしたものについて少しばかり愚考してみる。 |
| 2010/07/23「熟議に参加してみた」 |
|
文科省がすすめている「熟議」なるものがある。政策などにいかしたいなどの意見がでていたが、その真意はわからない。とりあえず、今回、テーマがやってきたので参加してみることにした。「熟議」で意見を述べるには字数制限があるので、ここでは、字数制限無視の形で意見を掲載しておく。「熟議」では、以下のことをまとめたものを掲載する。 |