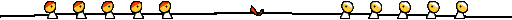教 育 コ ラ ム

| 2009/12/15「乞食はかくして姿を変える」 |
|
今年は政局面で大きな変化のあった年だった。自民党政権から民主党政権への移行である。民主党政権がいつまで続くかは予言者や専門家でもない僕にはわからない。民主党政権となって今までになかったパフォーマンスを見せてくれているのは興味深いところであり、今後歴史的にその正否が問われることになるのであろう。その一つとして、事業仕分けがある。いったいどういう基準で「仕分け人」が選別されているのかしらないが、それなりの人がそれぞれの「事業」について廃止や見直し、継続などいろいろを結論を下すのである。今までと比べると短時間で「結論」が下されるのでそれなりの人が評価する姿をテレビや新聞などで見かけた。 |
| 2009/12/06「数字だけで論じてみる」 |
|
11月30日に文科省から配信された新着情報メールの中にある報道発表の項に「平成20年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果(暴力行為、いじめ等)について」と題されたものがあった。どんな結果があるのか気になったので、早速調査結果を見ることにした。内容は50頁を超えるもので、各学校に対して行った調査の結果が詳細に記されていた。調査項目は、①暴力行為の状況、②いじめの状況、③出席停止の状況、④自殺の状況、⑤教育相談の状況の五つであった。
というものであった。最初の頁を見ただけで、これはマス・メディアが喜ぶ内容だなあと思っていたら、次の日(12月1日)の朝刊には記事となっていた。その内容は、報告書に出ていた数字をもとにみやすいように加工したものであった。僕は、是非とも新聞記事などではなく、報告書そのものを読んで見てもらいたいと思う。おそらく、伝わってくるものの感じ方が変わると思うからである。 |
| 2009/11/25「大人版学力テスト」 |
|
学力バカを喜ばせるような発表が先日あった。教育産業界が裏で手を引いているのか、新たなゲーム感覚のソフトを販売するためなのかは僕にはわからないが、少なくとも「学力」を信奉している連中にとっては興味をそそられるようなことであると思う。来年度の春に「国際成人力調査」を行う計画を文科省(?)がたてているようだ。
となっている。16~65歳を対象とした一種の「大人版学力テスト」と言えるだろう。「成人」の「読解力」・「数学力」・「ITを活用した問題解決能力」などを調査したところで本当に有益な結果が得られるのかは、大いに疑問であり、むしろこの結果を利用した教育産業がニタニタと笑う結果になるのではないだろうか。消費が落ち込んでいるからこういうところで消費を促そうという意図であるなら、それはそれなりに意義のあることなのかもしれない。
こんなテストで「社会が求める力」を「特定」して、それを「政策」に活かせるのか疑問ではあるが、頭のいい人たちにとっては可能なのであろう。そもそも、「社会が求める力」とは何なのかという定義づけも大切であるが、逆説的に考えると社会が求めない力が存在できるのか、と疑問がわく。宗教的な考えになるのかもしれないが、社会が求めない力は存在できず、何らかの必要性(求める力)があるからこそその「力」が存在できるのであって、必要性がなければ存在はできないだろうと思う。 |
| 2009/11/17「再び動き出した学力バカ」 |
|
僕がこのコラムで使用している「学力バカ」について一部の人たちには話題となっているらしい。「バカ」の語が過激であるとの意見、的を射ているとの意見、見方は様々であるが、僕は様々な意見があるであろうことは理解しつつも僕の考えに基づいてあえて使用する。「学力」に群がりそれを利用して「無責任」な行動をする者を「学力」バカであると規定して僕は使用している。その最たる対象者は誰かというと学力テストの一部の実施者とその結果などで右往左往する教育委員会と教職員?、そして無責任にも「学力」を使用して騒ぎ立てるマス・メディアなどの人々がそうであると僕は一方的に、偏見的に思うのである。 |
| 2009/11/02「お金を払うから私立」 |
|
私立は自分でお金をだして通うから私立であって、私立なのにお金がかからないというのであれば、公立となんらかわるところではない。 |
| 2009/10/21「何故素直に謝らぬ」 |
|
本日付で文科省が「教員免許更新制等の今後の在り方について」と声明を発表した。
以上の文章を読んで見てみなさんはどのように感じられただろうか。教育現場では、子供たちに間違ったこと、悪かったことは素直に謝ろう、と指導してるらしい。何故教育現場を司る最高峰の機関の人間は素直に「この制度はおかしかったです」と言って謝らないのだろう。頭を下げることにプライドが許さないというのであれば、せめて「認める」行為があってもいいのではないだろうか。 |
| 2009/10/19「奇策は良策とならず」 |
|
民主党政権が誕生して1ヶ月が経った。この間、いろいろな施策などが打ち出されて、その施策に対して是非がいろいろな場で話し合われているようである。一国の政治を執り動かすというのは大変なことだと思う。価値観が必ずしも一様ではなく、様々な価値観が存在し、αに対してはよい施策であっても、βに対してそうでないことが多々あるからだ。特にダム建設はそのような問題を多くはらんでいるようだ。 |
| 2009/10/10「公約の愚行」 |
|
『毎日新聞』夕刊のトップでも扱われていたが、来春にも扶養控除を民主党政権は廃止するという。政治特有の話のごちゃ混ぜでわかりにくいが、扶養控除の廃止と子ども手当を同じ土俵にのせるような形での議論、または連結された議論はすべきでない。あまり政治に関わったことをここで言うつもりはないので、政治の複雑なことについては自称専門家たちに任せるとして、教育上問題のあることに対して愚論を展開してみる。 |
| 2009/10/01「教員募集とブラック学校」 |
|
とうとう10月になりました。今年も残り2ヶ月というところだろうか。さて、この時期から年末にかけて私立学校の教職員募集がはじまるところが多い。募集があること自体は問題ではないが、この募集に関して一言付言しておこうと思う。 |