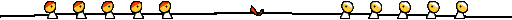教育に関するコメント

| 2008/06/28 「長期欠席者という数字」 |
|
最近、教育行政に関するややこしい話を載せる機会が多くなっていますが、最近、このコラムをつれづれなるままに書いているので、その点はご容赦していただきたいと思います。教育行政が教育崩壊の原因の一つでもあるということを考えると、ややこしい話でも少しばかりガマンしてつきあっていただきたいと思います。 |
| 2008/06/24 「北九州市教委に一言」 |
|
毎日新聞のネット版に「<北九州市>執行猶予中の講師採用 4月からの授業無効に」という記事が掲載されていました。一地方のチョットした記事ということで見過ごしかねない内容ですが、よくよく読んでみると教育委員会の対応のまずさに憤りを感じざるを得ません。雇用する時にしっかりと講師に対する調査をしていなかったことに対して批判もありましょう。しかし、事が起きてしまってから云々をいっても仕方がないでしょう。問題はその対応の仕方です。
以上がその全文です。僕が問題にしたいのは、「女性による授業は無効となり、1年生31人に26~48時間の補習が必要となる。学校側は夏・冬休みなどを使い補習をする」という箇所です。6月10日に「匿名の電話」によって判明したということですが、その匿名電話に対していささか不自然な臭いを感じざるを得ませんが、そのことはおいておいて、教育委員会の対応に話を絞りましょう。 |
| 2008/06/20 「助成金について考えてみよう」 |
|
先日、橋下知事知事による府の財政再建に関連して、私学の助成金も削減の対象となりました。そのことに関しては、以前よりここでコメントを載せいているとおりです。この件に関しては、橋下知事は消極的とみるのか、優しさの一端が現れたのかとみるのか、明確な意図は読み取りにくいところはありますが、僕としては、完全に補助金をなくすべきであると思っていますし、そう主張してきました。 |
| 2008/06/14 「ある女子高生の自殺」 |
|
こういう話題が尽きないのは悲しいことですが、先日、高校1年生が自殺を図りました。病院に搬送されたそうですが、残念ながら亡くなったそうです。 |
| 2008/06/11 「私学助成削減に関して」 |
|
教育問題研究所では、教育に関する情報を新聞やTV、そしてインターネット、時には官公庁から得ることがあります。特に、注意しているのは新聞やTV、そしてインターネットです。これらのメディアを通じてどのように物事が報じられているのか、そして、報道の仕方に問題があれば警鐘を鳴らしたり、内容そのものについてコメントをここで発表させて頂いています。 |
| 2008/06/10 「あれから7年…」 |
|
6月8日、東京秋葉原で17名が死傷する事件がありました。各メディアは相変わらずバカ騒ぎをして、容疑者が何も言えない場所にいることをいいことに好き勝手言い、好き勝手な憶測を並び立てています。「通り魔」というよりも無差別テロであると僕は思いますが、何はともあれ、事件に巻き込まれ亡くなった方の冥福を祈ります。秋葉原で凶行があった同日、大阪である集会が執り行われました。6月8日は大阪教育大付属池田小学校で殺傷事件がおこった日でもありました。2001年6月8日に発生した子供を対象とした卑劣な凶行は、決して許せるものではなく、僕自身、死刑という対応は生ぬるいのではないかとさえ思っています。 |
| 2008/06/09 「英語教育に関して」 |
|
前回、教育再生懇談会が打ち出した「まとめ」について、携帯電話に関連したことを述べました。今回は、その続きにとして、同じように「まとめ」で打ち出した「英語教育」に関連したことを述べたいと思います。
ある保護者と話をしていたときのことです。その方の子供さんは小学生でした。保護者は、「最近、小学校でも英語の授業やってるようやけど、まともに敬語も使えん子供に何が英語やねん!!まず、日本語をキッチリ教えてから英語の授業をした方がええんとちゃいますか?日本語も英語も中途半端なことしてどないしますねん」と関西弁丸出しで話してくれました。僕は、この方の話に賛成です。日本語が十分にできないうちから、英語を導入しても、日本語と英語を中途半端に獲得することになりかねないし、その可能性は高いと言えるでしょう。 |
| 2008/05/28 「子供携帯電話所持に関して」 |
|
今月26日に教育再生懇談会が6項目にわたる今まで審議の「まとめ」を発表しました。その内容は、
です。「質の高い留学生を受け入れる先進的な重点大学を30形成し、重点的支援を行う」というわけのわからん「国家戦略」を論じている3はおいておいて、ここでは1の「子供を有害情報から守る」という点に的を絞って話をすすめたいと思います。 |
| 2008/05/20 「初芝学園の不祥事の顛末」 |
|
昨今、様々なニュースが飛び交い膨大な情報量にチョット前の事件が、だいぶ昔の出来事のように思えてしまいます。2007年の7月に明るみとなりました初芝学園の問題を覚えていらっしゃるでしょうか?
以上のようなことを平然と行い、理事による学園の私物化が浮き彫りとなりました。僕はこの事件に対して、①理事による学園の私物化と言われるが、「教育」を行う場において教職員たちは今まで何も行動をとらなかったのか?②これだけの問題というよりも不祥事を起こしておきながら何ら「学校」としては処罰されないのか?③はたしてこのようなことは初芝学園だけの事なのだろうか? と三つの疑問を抱きました。①に関しては、わざわざ取材をするまでもなく、何もしていなかった、又は教職員が子供たちの前で偉そうに言っていることを実行していたらこのような結果にはならなかったのですから、実情を読者は想像できると思います。
大きくまとめると五つほどになります。ここで僕はたったこれだけのこと?と思わざるを得ませんでした。大阪府教育委員会は、初芝学園の不祥事に関して「公教育の一翼を担う学校法人としてあるまじきもの」と言っておきながらこれだけの対処しかしていないのです。学校教育法第1条の規定にある「学校」の指定(一条校)を取り消してもいいのではないかと僕は思っています。箇条書きの一番最後の「文書指導の中で要請した」と箇所があります。「文書指導」を中心に教育委員会は対処をしたようです。当研究所に対しての回答にもよく「文書指導」を行ったことが記されていますが、「公教育の一翼を担う学校法人としてあるまじき」行為を行った「学校」に対して「文書指導」と補助金の返還と補助金の減額ぐらいで、この事件を終わらすのはあまりにも大阪府教育委員会は責任感が薄いのではないかと思わざるを得ません。断固とした処置を何故行わないのでしょう。 |
| 2008/05/13 「文科省の呆れた考え」 |
|
先日より、TVでのニュース報道や新聞紙でチョットした話題として取り上げられているのが、GDP(国内総生産)に対する教育関連予算の増額を文科省が要求していることです。GDP比5%にしようというのが文科省の主張です。どこに根拠があるのか全く理解できませんが、報道などでは「教育費を今後10年間で経済協力開発機構諸国平均の5.0%へ引き上げる」ことを文科相が発言したといいます。経済協力開発機構(OECD)諸国とでてきましたが、みなさんはこのOECD加盟国をご存じでしょうか? |
| 2008/05/01 「青空学校の設立に関して」 |
|
昨年、12月に吹田市内でデイサービスを行っているNPO代表(訪れたらのはNPO代表とその両親でした後に判明することが、NPO代表といいつつも実質的に組織を握っているのがその母であることがわかりました。そこでこれ以降、代表とはその母を指すことと思ってください。)が訪れて、地域の子供たちに支援などに関して尽力してほしい、と依頼を受けて学校創りに取り組むことになったことは以前、ここで書きました。その経過報告をここで行いたいと思います。 |
| 2008/04/27 「わくわく子ども学校見学」 |
|
先日、箕面市で新しい学校創りを行っている「わくわく子ども学校」を見学させていただきました。その報告と考察をここでしたいと思います。 |
| 2008/04/12 「私学助成削減を賞賛する」 |
|
最近では、学校創りの方に専念して、教育問題研究所そっちのけで活動している代表です。活動内容としては、教育問題研究所でもっていた夢の一つを実現に向けて歩みをすすめているという認識に立っていますので、僕としては何ら不自然さなどは感じていません。むしろ、教育問題研究所の進化型として、学校の中に吸収してもいいのではないかとも思っていますが、組織のあり方としてはそう簡単なものではないようなので、とりあえず、今は二つの組織がある、という程度で進めています。
この記事の内容に関することは、『毎日新聞』にも掲載されいてましたが、私学助成の削減に関して、私学関係者から批判が寄せられているそうです。これに関して、今後取材を検討していますが(取材する意義があるか否かは別として…)、とりあえずコメントをよせておきます。 |
| 2008/04/02 「本年度スタート」 |
|
とうとう、2008年度がスタートしました。教育問題研究所では、昨日から新しく「学校」創りに取り組んでいます。きっちりとした枠はまだまだですが、大きな枠はできあがっています。既成概念にとらわれない学校創りです。新年度がスタートしたのを機に記事を更新しようと思いましたが、昨日は4月1日、エイプリルフールで、「嘘」だと思われると困るので、今日の更新となりました。 |