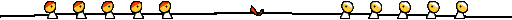教 育 コ ラ ム

| 2009/03/23「ぼかされた夢」 |
|
今から6年ほど前、2003年に公布された個人情報保護法がある。これは、「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的」とした法律であるが、何をどのように、どのような場合に於いて「個人」の「情報」を「保護」するのかが不明確なままで、具体的な事例があってもそれが企業のみなのか、学校に対しても一様に適用されるのか、などなど具体性もそれぞれに判断がゆだねられた状態で今に至っています。「事業者」というのがくせ者であることは当初から指摘されていました。
さらに、『毎日新聞』でも「若田光一さん 記念品小中生10万人写真に画像処理で規制」という見出しで記事が出ていました。『毎日新聞』の内容は、
写真処置に一ヶ月費やし、相応の金をかけて、何に努力をしているのか、疑問を抱かざるを得ません。特に関係者は、1万人のぼかし写真を受け取る若田さんの気持ちを考えなかったのでしょうか?宇宙に持って行ける物には制限があり、たったDVD一枚であってもそれを宇宙に持って行くことは貴重なことです。それを1万人のぼかし写真とは愚かにもほどがあるでしょう。「過剰な個人情報保護」というより、一言「愚か」です。全く無駄な金の使い方です。若田さんもとんだDVDを受け取ってことで苦笑いでしょう。 |
| 2009/02/27「派遣切りの陰で」 |
|
昨今、経済不況の下で派遣切りが取り沙汰されています。ここでは、経済問題や政治問題について取り上げる場ではないので、そのことについて詳細に触れるつもりはありません。しかし、経済不況の影響は教育現場にも影を落としているので、そのことに絡めて話をしてみようと思います。 |
| 2009/02/10「なぜ、ブラジル人学校」 |
|
先日来より、NHKのニュースで経済不況下で起きている、ブラジル人学校の経営不振やそこに通う子供達に視点をあてている特集をみることがたびたびありました。ブラジル人学校に通わせる親が、この経済不況で解雇や契約を打ち切られて、学校に通わせられないそうです。そして、子供達がブラジル人学校を辞めて、公立学校に通わせる事になっているそうです。番組では、「公立の受け入れ態勢は云々」と報じていました。 |
| 2009/01/29 「サイエンスコンプレックス」 |
|
先日来より本年度の公立高校の入試状況が報道されています。私立の出願状況、公立の出願状況などが報道されています。そのなかで、横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校の5.24倍の競争倍率が取り上げられ、「科学者育成」、「理系離れを防ぐ」為に設立されたサイエンスフロンティア高校の話題がTVでも取り上げられています。僕は一連の報道をみていて、日本の教育施策のおめでたさに呆れていました。わざわざ多額の税金をつぎ込んで何をやっているのやら…。理科系離れを防ぐためこれほどのことをしなくてはならないのか?それほどまでして科学者を育たなくてはならない理由は何か?わかりません。
この文章の何がおかしいの?といわれる人がいるかもしれませんが、ここまで高校で「人材を育成する」必要があるのでしょうか?この学校だけがここまで突出する必要があるのか僕には疑問です。もっと他に注意すべき事があるように思えます。 |
| 2009/01/26 「免許更新制の動向」 |
|
教員免許更新制に関する中間的報告が文科省より「平成21年度第1回免許状更新講習の認定について
」と題されてありました。当研究会では、教員免許更新制の導入に対しては、文科省にどの導入の明確な理由説明を要求し、その問題点を指摘してきました。くどいようですが、ここであえてもう一度取り上げようと思います。 |
| 2009/01/19 「横浜市の小中一貫について」 |
|
つい先日、横浜市で小中一貫教育に関することが報道されていました。各紙でも大なり小なりの違いはあっても記事となっていたと思います。その記事の内容とは、「小中のギャップ」を解消するために、市内の491校で小中一貫教育を導入するというものです。僕の考えは後におくとして、どのような内容なのかわかってもらうために、産経新聞と読売新聞の記事を見ていただきましょう。
以上が記事の抜粋です。この中で横浜市が小中一貫を導入する理由として大きく二つ取り上げられています。一つが中学校に入学することで授業についていけなくなることであり、もう一つが人間関係などの変化に対することで不安になることである。これらは所謂「中1ギャップ」と言われている。この中1ギャップへの対応、対策として打ち出されたのが小中一貫教育といってもいいと僕は思っているが、この小中一貫教育にはそもそも出発からして問題があると思う。ジャーナリストが指摘しているように、「教員が『学級』単位で担当する小学校と、『学科』単位の中学校とでは仕組みや文化が大きく違う」ことも大いに問題であるが、出発点の一つである「中1ギャップ」に対して大人はあまりにも無批判に、そして安易に答えを小中一貫という形で答えを出しすぎているのではないだろうか?僕からみるとあまりにも過保護的思考による安易な政策の導入としか思えない。 |
| 2009/01/06 「新年がスタート」 |
|
明けましておめでとうございます。年が明けて1週間が経とうとしています。はやいものですねえ。私事ですが、年末年始を殆ど家にいることなく、出歩いていました。出歩いていて感じたことは、経済不況の煽りなのか、不景気な雰囲気が伝わってくるようでした。そして、会う人と話をしていても不景気の話が出てくることが多かったです。 |