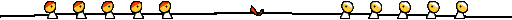教育に関するコメント

| 2008/03/15 「橋下知事に提言すること」 |
|
3月14日の『毎日新聞』の一面記事を読んで、腰の重い僕が珍しく、「これはいかん!早速、コメントを載せないと」と思い、PCの前に座って、「コメント」を作成しています。
先日、橋下さんの議会での発言削除がマス・メディアに取り上げられ、メディアがバカ騒ぎしていました。その際に、教育委員会に「指示する」という発言が問題があるというように出ておりましたが、教育委員会とは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき設置された合議制の執行機関で、基本的には首長からは独立しております。「基本的」というのがポイントで、独立といいつつも太鼓持ち的な性格を今は有しているといっても過言ではない、教育委員会もありますから…。さて、大阪府の教育委員会は独立の姿勢をもって、教育行政を展開できるのか…。 |
| 2008/03/08 「橋下知事に期待すること」 |
|
教育問題研究所では、政治的発言を行う場ではないと考え、今まで極力政治的な発言をすることを控えてきました。しかし、今年になって大阪府知事に就任した橋下知事に関する報道を見ていて、気になるところがありましたので、少し意見を出してみようと書くことにしました。そうはいっても、○○政党が…とか、政治的なことを言うつもりはありません。あくまでも教育に限定してという点で、橋下知事に対して意見を表明しようと思います。
僕は、橋下知事の施策全てに興味があるわけではないし、橋下知事が今後どのようにその手腕を振るうかは未知数なので、いいとも、悪いとも思っていません。ただ、「教育日本一」をうたうのであるなら、塾と学校を利権の巣窟にするようなことだけはしてほしくないと思っています。杉並区和田中学の藤原校長を教育担当顧問に据えるということで、大阪に偏差値偏向教育が復活し、大阪に教育利権を今以上に招くことになるのではないかと危惧します。藤原校長の人格云々をここで言うつもりはありませんし、会ったこともない人ですから、そんな権利を僕は持っていません。ただ、「夜スペ」で示されていますように、教育利権になりかねない状況、むしろすでにできあがっていると思いますが…。教育産業の発展にはなっても、それ以上のものはないようなことを大阪で展開してほしくないと僕は考えています。 |
| 2008/02/25 「日本史必修科について」 |
|
たまたま、うちでとっている2月16日付の『毎日新聞』に、神奈川県の公立高校で日本史を必修科することを伝えていました。「愛国心」を植えつける云々と批判もでているようですが、僕は世界史の必修よりも日本史の必修が必要であると考えていましたので、神奈川県の教委がとった事に対しては目的がどこにおかれているかは、さておき評価したいと考えいています。 |
| 2008/02/13 「大きな一歩となるか…」 |
|
『毎日新聞』の2月7付夕刊の記事に「フリースクール公認」という大見出しで、京都府教育委員会がフリースクールで受けたカリキュラムを成績や内申書に反映させることを発表した、という内容のことが記されていました。記事全文に関してはここに掲載しておきます。この日には程度の差はあれ各紙でも取り上げられていたようです。代表して共同通信社の記事では、 |
| 2008/01/27 「学校と塾に関して」 |
|
今日から東京都杉並区の和田中学で「夜スペ」がスタートしました。新聞では、「学校塾」と言葉が用いられていました。学校と塾が合わさって「学校塾」。今の混沌とした教育界を象徴するような言葉であると思います。学校なのか、塾なのか、よくわからないもの。学校と塾のいいところを集めたもの、学校と塾のいい部分のエッセンスを混ぜたもの、と表現することは可能ですが、教育上そんなことがあり得るのでしょうか?現実的に和田中学では起きているのですから現実このことなのですが…。 |
| 2008/01/20 「責任のありかた」 |
|
新年が明け、今年ももう20日が過ぎようとしています。新聞記事やテレビ報道、そしてネット記事からは様々な事件に関するニュースが流れてきます。よくもまあ、こんなに世の中にはいろいろ話題に困らないほどネタがあるなあ、と思わされます。ニュースには微笑ましいものもあれば、笑ってすませられる記事、なるほどと感心させられる記事もあります。そして、痛ましい記事も…。 |