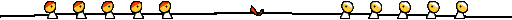|
先日、毎日新聞の記事に「野菜廃棄もったいない」という記事がありました。昨年末より時々耳にした「野菜廃棄」という言葉に僕はかなり違和感を覚えました。僕の記憶では、昨年末にキャベツが豊作ということで廃棄するというニュースがテレビで流れてました。調べてみると、9710㌧を廃棄したそうです。kgではありません「t」です。想像もできない量ですが、その大量のキャベツがどうなったのか?虫に食われたとか、天候など影響によって被害を被ったという事ではありません。単に「豊作」だったから「廃棄」するのです。僕には未だに理屈がわかりません。「豊作」だから「廃棄」。「豊作」になると農家の人にとっては「困る」ようです。
たくさんの野菜がとれたら、その分だけ価格が下がるというのは理解できます。でも、それだけで「廃棄」するというのは問題があると思います。学校や家庭で子供が食べ物を残すと「なんで残すの?世界には食べたくても食べられない人がいるんやで」という言葉を一度は聞いた、聞かされたことがあると思います。食糧難で食べたくても食べられない人がいるのに、片方では「豊作」で価格が下落することを恐れて「廃棄」するという、それこそ「もったいない」行為がされています。子供が遊び半分で食べ物を粗末にしているというレベルの話ではありません。大人が「真剣」に食べ物を価格下落という理由だけで「廃棄」=捨てているのです。
このようなことが何ら問題とされず、単なるニュースとして情報が配信されていることに僕は違和感を覚えます。最近では、未成年の犯罪、凶悪犯罪などのニュースに慣れてきて、このようなニュースには鈍感になりやすくなっていますが、もっともっとこういうニュースには敏感になってないといけないのでは?と思います。
みなさんは、以上のことをどのように思われますか?感想を掲示板にでも書き込んでいただけたら助かります。
夏に行われる祭り、夏祭りは神社や夜店を潤わすための行事ではありません。「豊作」を祈願して行われる行事です。そして、秋に行われる祭りは「豊作」を神に感謝するためのものです。今での意識されているか否かは別として、「豊作」を祈る、感謝する行事が日本の各地に残っています。
11月23日は祝日ですが、何の日かご存じですか? 勤労感謝の日です。働いている人に感謝するらしいのですが、この勤労感謝の日が設定されたのは1948年以降の事です。それ以前は、どのように言われていたのか?新嘗祭(にいなめさい)として知られていました。社会科の試験で漢字で答えさせるような言葉ですが、この新嘗祭は、「新穀を神にささげて収穫を感謝し、きたるべき年の豊穣を祈る」祭りなのです。
「豊穣」を祈り、その結果大地の恵みによって「豊作」になったら価格が下落するという理由で「廃棄」するとは、なんと悲しい、お粗末な話でしょうか。「最近の若い子は豊かな時代で食べ物を粗末にする、うちらの時は芋のツルを食べていたのに」といっていたおばちゃんがいましたが、大人も粗末にしているのです。それも食糧難を経験したであろう世代の人が。「豊作」で食べ物を「廃棄」しないよういい知恵を出し合って、どうすればいいのか考えましょう。
今、農林水産省生産局野菜課企画班が「産地廃棄」についてアイデアを募集しています。締め切りは今月23日までですが、なんでこんな事に締め切りがあるんでしょうねえ。本気で取り組む気があるのでしょうか?
|

 意見募集要領
意見募集要領