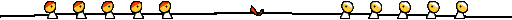教育に関するコメント

| 2006/12/25 「塾は必要か?」 |
|
12月24日「時事通信」の配信記事に「野依座長「塾は禁止に」と主張=報告案には盛られず-教育再生会議」という見出しの記事がありました。内容は、 「塾はできない子が行くためには必要だが、普通以上の子どもは塾禁止にすべきだ」。政府の教育再生会議分科会で、座長を務める野依良治・理化学研究所理事長が「塾の禁止」を唱えていたことが、同会議ホームページに掲載された議事録で24日明らかになった。ただ、委員の間では賛否が分かれ、21日に公表された中間報告原案には盛り込まれなかった。 とういものです。欧米では日本のような塾という施設・機関は珍しいです。何故、「塾が必要なのか?」塾依存型の日本社会というものを保護者や学校、子供たちも冷静に考えなくてはならないでしょう。 野依氏は「塾はできない子が行くため」という認識を示しています。塾が発生した当初もそんな感じだったのでしょう。では、できない子とはどんな子なのでしょう。算数ができない、国語ができない、社会ができない、理科ができないということなのでしょう。その「できない」とはどのような状況なのでしょうか。「テストで点数をとれない」というように定義すればテストで満足な点数をとれない子が通うのが「塾」ということになるでしょう。すると、もう一つの視点である疑問があります。「できない子」に対して学校は、教師は今までどうしてきたのでしょう。 僕自身が教師として教壇に立っていたときに「大学受験の勉強をしたいのなら塾や予備校に行きなさい、そうすれば合格するための技術を教えてくれる、でもそれはその教科を理解したということではないからね」と言ってきました。テストで点数をとれない子に対して点数をとれるようにするところが塾なら点数をとるための技術を教えることになるでしょう。実際に新聞広告などで折り込まれている塾の広告を見ると、大手の塾は、「過去の膨大なデーターを基に有能な講師がテキストを作成し、指導しています」というようなうたい文句を入れています。過去の膨大なデータを基にどのようなテスト、どうすれば合格できるか、ということを追求したテキストや授業を行っているのが塾の基本的スタイルです。点数をとるために特化した機関が塾であると僕は思っています。 学校は、「できない子」のためにどのように取り組むかということも重要ですが、「できない子」もいてもいい環境作り、そして「できない子」という概念そのものを見直さなければならないと思います。「できない子」=「社会でダメな人間」のような見方が学校や家庭、社会で行われているからこそ塾の存在理由があるのです。できなければできるまでじっくりできる環境と意識が必要でしょう。 日本の義務教育は、どんなに実力がなくても進級できてしまうシステムです。小学生にとって九九もできないのにそのまま進級することは、ある意味でむごいことです。進級できる実力を備えてないのに「進級させられる」のですから。そうすると、何とか学力をつけてと「他の子と一緒に」「普通のように」という親心が働き塾に通わせてしまう場合もあります。また、学校は「遅れている子」を中心に授業を進めるから「できる子」には「つまらない」ということでもっと早い段階で、もっと高度なものをという思いから塾に通うという例もあるようです。最近では、共働きで両親が遅くに帰ってくるから帰宅して親が帰ってくる間、学童感覚で塾に通わすということもあるようです。 塾に通わすきっかけは今では様々ですが、そもそも塾に通わさなければならないような社会のあり方を大人たちは再考し、問うていかなくてはならないでしょう。「できない子」が行かなければならない塾なら「できない子」を受け入れる社会とアメリカの義務教育のように何度でも「できる」まで挑戦できるシステムを考える必要があるし、「できる」子がつまらないと思って塾に通うのであれば飛び級のようなシステムを考え、何でもかんでも「同じ」「同質」を求める体質を考え直す必要があるでしょう。そして、学童のように利用するなから家族のあり方をもっと、家庭だけでなく労働市場でも考えていく姿勢が必要だと思います。「今の子供たちは」「今の教育環境は」……、マス・メディアを代表として様々に議論されています。本当に子供のことを考えるなら、家庭のことを考えるなら、仕事を中心としたあり方、従業員を駒のようしか考えていない労働市場のあり方を考えなくてはならないでしょう。会社に託児所を設けて残業をしやすい環境をつくるより、早く家に帰られるような環境作りが必要ではないでしょうか? 大人が「子供のために」と心底から思うなら、言葉だけでなく真剣に取り組む姿勢を示すことが必要だと思います。僕の好きな言葉の一つに「移木の信」というのがあります。言ったこと約束したことを守るという意味ですが、「移木の信」を実行できている大人がどれほどいるのでしょうか? |
| 2006/12/20 「教育基本法改正について思うこと」 |
|
19日に国会が閉会しました。国会ではいくつかの法案が可決されましたが、その中に「改正教育基本法」が成立しました。19日の閣議で改正教育基本法を22日公布・施行するということが決まったそうです。  「改正教育基本法」 「改正教育基本法」
|
| 2006/12/13 「免許更新制について本質的な議論を」 |
|
安倍晋三首相が13日の衆院教育基本法特別委員会で、教員の質の確保に関連し「(教員の中に)不適格であるという方々がいるのも事実。採用する際には資質が十分に分からなかったという例もある」と発言したそうです。以前からも教員免許の更新に関しては問題提起をしてきましたが、教育再生会議では問題の本質を何ら考え、それを提言することなく、免許の更新制を導入をさせようとしています。100%の人間が全て納得するということはあり得ませんが、ある程度の人たちが聞いて納得できる理論が必要であると僕は思います。 教員の資質能力の向上を図るため、教員養成課程から任用、評価、研修など、総合的に捉え検討する。また、指導力と人間力を備えた、熱意ある人材を、社会人経験者など教育界の外部に積極的に求め、教員集団を多様化する。
という言葉があります。この一段落の言葉一つをとっても疑問がいくつかわいてきます。①教員養成課程で誰が「総合的に捉え検討」するのか?②「指導力と人間力を備えた」人間をどのように判断するのか?③「社会人経験者など」が「指導力と人間力を備えた」人間なら現職の人間はどう判断されるべきなのか?④社会人とは「企業」につとめたことがあるということで、私立学校経験者、講師として実力を持っている人、さらにはフリーターとしての経験者やパート・アルバイトで今まで生活を余儀なくされていた人には「指導力と人間力」を備えていないと判断するのでしょうか? |
| 2006/12/06 「生きるということ」 |
|
今まで、いじめや自殺についていくつかコメントしてきました。ここで少し違った形でコメントを残したいと考えます。最初のホームにも書いてありますが、自殺をするのは自由です。自分の死に対して自身で決めるということですから、見方によっては選択不可能な誕生と違って選択可能な死というのは大切なのかもしれません。選択可能であるからこそ、その行為に対する責任は重大とも言えます。でも、自分ではどうしようもない「死」というのもあります。 |
| 2006/12/06 「学校や教師の解決能力」 |
|
「毎日新聞」2006年12月4日付けに夕刊21面に縦3.5cm×横10cmの小さな記事が載ってました。記事のタイトルは「教諭にけが 中2を逮捕」で、内容は兵庫県姫路市にあるある中学校で生徒が教諭に「腹部打撲のけがを負わせた」というものでした。今では、別に珍しい記事ではないように思えるのが怖いのですが、いつの頃から生徒が教師に暴力をふるって、警察を呼ぶということになったのでしょうか?あまりにも懐古的なことをいうつもりはありませんが、学校で起きたことは学校である程度解決してきたはずなのに、何かあればすぐに警察に通報する世の中となってきました。 |
| 2006/12/04 「子供のいじめ、大人のいじめ」 |
|
今日の「毎日新聞」に「大人のいじめも深刻」と題された記事が掲載されていました。先日、僕の住む町の喫茶店でちょっとした地域の人たちとの集まりがあってそれに参加させてもらいました。集まりといっても、小規模で地域の人たちが食べ物や飲み物を持ち寄っていろんなことを話し合ったり、何かイベントのことを話したりしているものです。
僕は、その席上でたまたま教育についての話、特に「いじめ」についての話題になったので持論をそこで展開させました。その中で、「子供のいじめばかりを問題にしているけど、大人の社会にあるいじめも問題なんです。子供は大人の社会を反映する鏡です。子供社会におかしさがあるのは大人社会がおかしいからで、いじめも学校のことのみが取り上げられるけど、大人社会でのいじめがほとんど取り上げられず、子供は様々な相談する機関が設置されているけど、大人の場合は相談する機関すら整備されていないというのが実情です」ということを話しました。新聞で今日、記事として取り上げられたので、これは書いておこうと思って、これまた重い腰をあげて書いております。 「大人のいじめ」もまん延しています-。日本労働弁護団(宮里邦雄会長)の実施する労働相談で、職場でのいじめに関する相談件数が全体の2割近くを占め続けている。内容も言葉のいじめから直接的な暴力まであり、弁護団は「子どものいじめ自殺が相次ぐ中、『子は親を映す鏡』というが、長時間労働などが職場にギスギスした雰囲気を生み、いじめにつながっているのでは」と分析。「14年間の相談活動の中で経験したことのない異常事態」と指摘している。 というものです。僕は、HPでは文章化こそしてきませんでしたが、会う人に「子供の社会は大人社会の鏡である」「子供の問題は大人の問題でもある」と言い続けてきました。学校での出来事は、会社などで起きていることと類似しているケースが多いと僕は思っています。
今、思い当たるのはこれくらいですが、これだけでも内容としては十分ではないかと思えます。本当に次の時代を担う子供たちを何とかしたい、と思うのであれば箱物のように制度ばかり上から押しつけるのではなく、大人そのものが行動を子供たちの前で示すべきではないでしょうか。子供目は純粋に大人の社会をとらえ、模倣していきます。僕の息子は保育園に通っていますが、その保育園に通う子供たちは小さいながらも十分に大人をまねています。特に言葉遣いなどはその典型です。何かをつくる、何かを設置するということで本当に問題の本質を改善することはできないと思います。大人の皆さん、保護者の皆さん、本当に子供の前で胸を張って語れるような社会を作っていますか?社会で生きていますか?社会ですか? |
| 2006/12/01 「緊急提言の中身」 |
|
-教育関係者、国民に向けて- 平成18 年11 月29日
教育再生会議有識者委員一同 すべての子どもにとって学校は安心、安全で楽しい場所でなければなりません。保護者にとっても、大切な子どもを預ける学校で、子どもの心身が守られ、笑顔で子どもが学校から帰宅することが、何より重要なことです。学校でいじめが起こらないようにすること、いじめが起こった場合に速やかに解消することの第1 次的責任は校長、教頭、教員にあります。さらに、各家庭や地域の一人一人が当事者意識を持ち、いじめを解決していく環境を整える責任を負っています。教育再生会議有識者委員一同は、いじめを生む素地をつくらず、いじめを受け、苦しんでいる子どもを救い、さらに、いじめによって子どもが命を絶つという痛ましい事件を何としても食い止めるため、学校のみに任せず、教育委員会の関係者、保護者、地域を含むすべての人々が「社会総がかり」で早急に取り組む必要があると考え、美しい国づくりのために、緊急に以下のことを提言します。
~学校に、いじめを訴えやすい場所や仕組みを設けるなどの工夫を~ ~徹底的に調査を行い、いじめを絶対に許さない姿勢を学校全体に示す~ ~東京都、神奈川県にならい、全国の教育委員会で検討し、教員の責任を明確に~ ~いじめが発生するのは悪い学校ではない。いじめを解決するのがいい学校との認識を徹底する。いじめやクラス・マネジメントへの取組みを学校評価、教員評価にも盛り込む。~ |
| 2006/12/01 「保健室って…」 |
|
掲示板に保健室の利用についての話が出てきたので、少しここで思うことを書いてみたいと思います。 保健室をケガなどによる利用だけでなく、メンタルケアとしての保健室をおかしい、無駄、不必要、とは思いません。僕が生徒だったときから保健室にメンタルなことで通う子はいましたしたし、それを「ずるい」「逃げてる」とも思ったこともありませんでした。時には保健室のような場も必要なんだなあ、と思うぐらいでした。生徒をしていた時は「なんで保健室にいかなあかんねんやろ」ということでした。教師っていったいなに?なんで担任などは対応してないんやろ?と漠然と思っていました。 僕は実際に教師になって、保健室に行かなくてもいいような状況をなるべく作ることではないか?と思うようになりました。僕は教師こそが生徒にとって「非常時」の「逃げ場」だと思っています。それを多忙などを理由に生徒の「逃げ場」を保健室へと放り投げてもいいのでしょうか?忙しいということなら労働環境として問題のあることを毅然として管理職に訴えていく態度が必要なのではないでしょうか?特に私立では教育現場は労働環境としては最低なところが多いです。権利などを教育する場でありながら、権利・人権を無視するようなことが平然と行われます。ここでは細かく具体例を挙げませんが…。 教師は口だけで実際に行動に移す人は少ないです。何でも相談にしにおいで、といいながら相談に行くと「忙しい」と断っている人。権利や人権を語っていながら自身は他人の権利を無視している人。いじめはよくないといいながら同じ職場の人間をいじめる人。人の相談にも「そうなんや」「ひどいなあ」と同意してくれるのにいざとなれば何にも協力してくれず「そんなもんや」と納得させようとする人。傍観者的存在の教師。いろいろみてきました。 ここまで書いて僕自身は人に言えるだけのことをしたのか、やめといて無責任なことをいうなといわれそうです。それに対してあえて否定はしません。僕自身限界を感じ、責任をもとるつもりで辞めましたから。 かなりまとまりのない文章となってしまいました。かなり恥ずかしいですが、正直な気持ちです。これを読んで何かを感じた方が掲示板に書き込んでくれることを期待します。 |
☆過去ログ☆
| 2006年6月 | 2006年7月 | 2006年8月 | 2006年9月 | 2006年10月 | 2006年11月 |