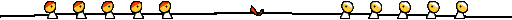|
最近、新聞を見ていても教育に関する記事を見ないということがほとんどありません。特に五大紙を見れば必ずどこかに教育関連の記事を目にします。事実、このHPの「1週間の主な出来事」にも全く書くことがなったということはありませんでした。
今日の『毎日新聞』に特筆すべき記事が掲載されていたので、そのことを取り上げたいと思います。「少人数学級:完全実施へ調整 合意あれば予算計上−−新年度から県教委 /滋賀」と題された記事の内容は以下のとおりです。
◇新年度から小学3年生
県教委は新年度から、小学校3年生で35人以下の少人数学級を新たに完全実施する方向で調整に入った。県内部で了解が得られれば、少人数化に伴う教員の人件費約2億6000万円を07年度当初予算案に盛り込む。06年度に小3で少人数学級を完全実施しているのは、全国で山形、長野、和歌山、高知の4県だけ。
現在、県では、▽小1▽小2▽中1の3学年に加えて、小学3〜6年のうち1学年を学校ごとに選んで少人数学級を実施。来年度からは、計4学年を固定化する他、小学4〜6年から1学年を選ぶ形で少人数教育を行うことになる。
嘉田由紀子知事は昨年7月の知事選で、マニフェストに「07年から全小中学校での少人数学級の完全実施」を掲げていたが、人件費の見込み違いなどから完全実施は実現しなかった。
マニフェストに示した項目では、発達障害を抱える生徒への支援の拡充も進める方針だ。現在、自閉症、学習障害などに対応し、コミュニケーション能力の指導などを行う教室が県内に25あるが、地域的に偏りがあるのが課題。地域のバランスに配慮して新たに4教室を加えるため、配置する教員の人件費などを予算要求している。【高橋隆輔】
記事では、滋賀県では「人件費の見込み違いなどから完全実施は実現」にはいたらなかったけれども、部分的には少人数学級を目指していくというものでした。僕は以前より、教育改革をうたうのであれば少人数学級の成立をも目指すべきであることを主張してきました。今回、縁があってある市の議員に立候補する予定ですが、僕はそのことをずっと訴え続けています。35人といわず、大胆に25人学級を欧米なみの25人学級を目指せばいいと思います。余計な公共事業に何十億と使い込むより、次の社会を担う若い世代の為に先行投資をすることの方が大切だと思います。
昔は、40人以上1クラスにいたと言われますが、今は全く昔と環境・状況が異なります。いじめの仕方一つにしても、一昔ではあり得なかった、携帯メールを利用したいじめなどその方法と内容は変わっています。まして、教師も昔のような一本気のある教師がどれほど残っているでしょうか?生徒のために、と管理職と親と真剣に取り組む教師は往々にしてうとまれています。まして、それが非常勤や常勤講師なら契約満期を理由に切られるということがあります。僕の知っている非常勤講師は「優秀だから辞めてほしい」とわけのわからない理由をつけられ契約満期で学校を去らなければなりませんでした。
先日も、教師が児童をたたき保護者が警察に傷害として被害届を出したという記事が新聞に載っていました。たたいた詳しいいきさつはわかりませんが、昔ならあり得なかったことです。いきなり警察に被害届なんて…。
話がそれましたが、教師の雑務が多くなり、教師自身に「ゆとり」のない環境で働いていますから、当然、1クラスに40人生徒がいてもしっかりと目が行き届くわけがありません。読者のみなさん自身を置き換えて考えてみてください、40人という人間をしっかり観察することができますか?ましてその観察結果が人生に大きな影響を与える可能性が大きかったら、その責任を背負ってみること、評価することができますか?会社で管理職に就いている人なら「みれる」と言われるかもしれませんが、「みれる」という人には直接お会いして、是非、どのようにしたらみられるのかお話しをお聞きしたいと思います。僕は到底無理だと思っていますので。
教育指導要領の改正や教科単位、時間数などいろいろ議論するのはかまいませんが、何故少人数学級についての議論が大きく取りざたされないのでしょうか?僕は、小学校の時1クラス17人という環境で育ちました。今はなき梅田東小学校です。児童数が少なすぎるというのも問題ですが、多すぎるというのも問題があります。学級数だけを議論にする教育委員会もあるようですが、もっと視点を大きくもって子供たちにとって良い環境とは何かを追求し、整備することが現在の課題でしょう。
どうか、教育改革をとなえる自称専門家や自称評論家の方々、是非少人数学級についての議論を活発にしてください。最近では、35人学級を!という署名活動も下火になり、そんなことを真剣にとなえる人が少なくなってきているように思えます。僕の気のせいならいいのですが…。
少人数学級はお金がかかるというのでしたら、お金の使い道を吟味し、どうしてもお金がないのならないなりのやり方があると思います。それは、先日行われた夕張市のお手製成人式を見れば、お金はないならないなりのやり方で最高の成果をもたらすことができるということを示していると思います。
|

 第1 次報告(骨子案)
第1 次報告(骨子案)