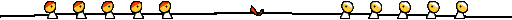教育に関するコメント

| 2008/09/30 「公表と非公表に意味があるの?」 |
|
9月24日に僕の住む吹田市では、学テの開示に関して、「非公表」を決定しました。無条件に公表した自治体と異なり、大阪府下では珍しく明確に非公表の意思表示を吹田市はしたと思います。非公表となった理由としては、「過当競争を招く可能性がある」からだそうです。「数値の公表が弊害になる可能性が高い」という意見が教育委員からも出ているそうです。 |
| 2008/09/17 「全テ、情報公開」 |
|
最近、大阪では橋下知事のおかげで「教育」に関するネタに事欠くことがなく、こちらとしては記事を書きやすいのですごく助かっています。橋下知事さんに感謝です。ありがとう。 |
| 2008/09/10 「教育非常事態宣言の投げかけるもの」 |
|
今月7日に橋下知事が「クソ教委」という言葉を使用したということで、毎日のように報道がなされていますが、あまのじゃくな僕としては、また「クソ」メディア(おっと、失礼!!)がわけのわからん報道をしていると思うと同時に、このことによって政治的に重要事項の報道を怠っているのでは?と邪推したくもなりました。今日の夕刊には、「オカンに怒られたからやめる」と「クソ教委」発言に対する「反省」をしたことが伝えられていました。これを僕は「反省」と受け止めることはできません。「オカンに怒られたから」「クソ教委」発言を撤回するのであって、不適切な表現であったのか否かはココでは問われないのですから。
|
| 2008/09/02 「非常事態宣言」 |
|
今の時代は便利なのか余計な情報があふれているとみるのか人それぞれですが、昨日、たまたまYahoo!をみると、ニュースの記事に「橋下知事、教育非常事態宣言も」という見出しが出ていました。また、猪突猛進型の橋下知事のことですから、さぞ「教育」に対する想いを形にしていくのかと期待して記事を読んでみると、さすが偏差値偏向世代と思わされる内容で、妙に納得させられました。記事の内容を示しますと、
というものです。橋下知事は、全国学力テストの結果が、小学校で41番と中学校で45番になったことを「恥」だと思っているのでしょうか?橋下知事は、プライドの高い、インテリのように耐え難い屈辱と受け止めるような方ではないと僕は思っています。まさか、そうのように受け止めてないですよね。何が、どのような非常事態なのかということを明確にすべきであると思います。そして、それが「点数が低い」ことを非常事態というのであれば、二昔前の偏差値至上主義時代へと逆戻りしかねないことになるかもしれません。今度、大阪府下の市町村で「成績」を重んじるような事になっては、教育環境は荒廃するのみではないかと思います。 |
| 2008/08/19 「ある投書」 |
|
今回は、『毎日新聞』に掲載された投書を題材に教員の人事に絡む贈収賄について考えてみたいと思います。まず、『毎日新聞』に掲載された投書を以下に掲載します。
という記事です。この当初は、教育の世界では贈収賄は当たり前のことのように書かれています。そして、そのことから大事なことも示唆しています。それは、教員採用試験のあり方の問題です。教員の採用システムを根本的に見直して、改革をしないといけない、と現場や文科省に言ってきました。教員免許更新制というアホなシステムを導入する以前にもっとしなくてはならないことがあると思います。文科省の連中や自称専門家は、自分たちには関係ないと思っているようですが、裏金問題などに絡んで、公務員も10年に一度の試験を実施してみればいいのです。そして、それで公務員の質が向上するのか考えてみたらいいのです。そんなことで向上するなら誰も苦労はしません。 |
| 2008/08/11 「大阪版夜スペ実施決定?」 |
|
前回のコメントで大阪に「夜スペ」を導入することに関して、僕なりの考察を載せました。そして、僕がかみさんの田舎に行っている間に、大阪版夜スペの導入が決まったような記事が掲載されていました。あまりにも急なことというよりも、迅速な対応に違和感を覚えつつ、記事に目を通していました。教育に関することは、マスメディアも無責任に言いたい放題やりたい放題できますし、それに便乗するように行政側も「教育」を掲げて予算獲得などをしているように見えるのはあまのじゃく的すぎるのでしょうか…。
かなり長い引用でしたがこの記事には、大人の理屈を子供達に押しつけている様子が受け取ることができます。「小中学校の全学年を対象に、元教員や教職を目指す大学生、塾講師の指導のもと、放課後に1日2時間、週2回の補習授業」をすることによって「学力」があがるというのであれば、その「学力」とは何なのでしょうか?算数や数学の点数をとれることが「学力」があるというのでしょうか? |
| 2008/07/28 「大阪に「夜スペ」!!」 |
|
大分県の収賄事件に関してさらなる続きを書こうと思っていましたが、大阪府がアホなことを考えいてるということをTVのニュースと新聞の夕刊でみて、急遽、予定を変更して大阪府と便乗しようとしている池田市の愚行に関して、あまのじゃく的意見を述べたいと思います。 大阪府池田市が、生徒の学力向上を目指して東京都杉並区立和田中学校が行っている有料の夜間特別授業「夜スペシャル(夜スペ)」を参考に、外部講師による課外授業を検討していることが28日、分かった。
TVの報道とはニュアンスが異なるかもしれませんが、とりあえず、「学力向上」を狙って授業を放課後以降に展開する、ということをわかっていただけたら十分です。教育産業のとの癒着として有料か無料かという議論は少し置いておいて、もし、「夜スペ」を実施するのであれば、教育予算を削っておいて特定の「できる子」に対して予算をかけるという摩訶不思議なことを橋下さんは推進するのでしょうか?もしくは、池田市はよほど予算が余っているのでしょうか?僕には不思議です。 |
| 2008/07/21 「続・大分県の収賄汚職について」 |
|
前回にコメント掲載してから1週間が経ちました。その間、大分県の収賄事件に関して様々な報道がなされました。教員採用に始まり、昇進人事に関することまで、多様な事件となりました。その間の報道内容といったら、採用に不正が起きないようなシステムと不正をした教育委員会に対する批判と学校教育に対する不信感云々ということなどが大半を占めていました。飛騨牛の偽装事件は、遠い過去のように忘れ去られ、大分県教委の不祥事に対して一斉に攻撃を行っています。まるで一種のリンチのようにさえ見えます。 |
| 2008/07/14 「大分県の収賄汚職について」 |
|
7月5日から6日にかけて新聞などのにとりあげられました大分県教委汚職について今回はコメントをしたいと思います。7月5日(土)から6日(日)はちょうど週末ということもあって、TVなどではあまりニュースを見る機会はありませんでした。しかし、週明けの月曜日である7日以降からはワイドショーを始め各所で大分県の教員採用試験を巡る汚職に関してのニュースがクローズアップされ、時間の経過とともにその扱われ方は大きくなっていきました。事件は、大分県での教職員の採用を巡り、県教委参事をはじめ、当時の県教委審議監そして何名かの校長や教頭までが金品の授受によって採用されたり昇進にまで関与したという内容のものです。 |
| 2008/07/08 「大学のあり方」 |
|
前回の「大学のあり方」の続きになるかもしれません。7月6日付けで「「学生の基礎学力ない」理系教員の7割指摘」と題する記事が小さく出ておりました。日曜日の3面記事に小さく出ていたのですから、どれほどの方が目にとめられたでしょうか。 |
| 2008/07/03 「大学のあり方」 |
|
少し古い話となりますが、約一ヶ月ほど前に、「発掘調査も「資格」の時代?」と題された記事が掲載されました。内容は、遺跡の発掘に資格が必要ではないか、という議論がわき起こっていることを伝え、日本文化財保護協会が運用する資格と文科省から委託を受けた早稲田大学が行う「考古調査士養成プログラム」という二つの資格の事例を挙げています。 考古学コースは、他の歴史学と同じように人類の歴史の解明と理解とを目的としている。そのため文献史学と違って文字ばかりでなく、過去の人類が残したさまざまな物、遺跡や遺構、遺物などの物質資料によって研究、学習する点に特色がある。
記事には、資格が求められる背景として、「発掘の多くを担う自治体の実務者のうち26~27%は考古学専攻経験がなく、専門職員のいない市町村も5割に達する。このため現場からは「社会の信頼を得るためには資格が必要」との要望」があったからと伝えています。これは、資格制度の問題ではなく、自治体のあり方にも問題があると言わざるを得ません。考古学を専門とする人間を雇えばいいのです。そんな予算がないから、資格制度を作り、専門でない人間に「資格」をとらせてコストを低く抑えようというつもりなのでしょうか?いくら資格を取得しても専門でない者は所詮それまでです。 |