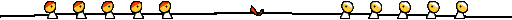教育に関するコメント
2007年5月〜12月
| 2007/12/14 「ある人との出会いから」 |
|
単位未履修や野球特待生について取り上げてきましたが、今回は少し趣向をかえます。随筆にようになってしまいますが、たまにはこういうのもいいかなあ、と思いますので書きます。 |
| 2007/11/19 「単位未履修が問いかけること」 |
|
『毎日新聞』の11月17日付け朝刊に小さな記事が出ていました。たまたま職場には『朝日新聞』が入っているのですが、同じ記事が小さく扱われていました。『毎日新聞』でも見出しは、「未履修解消せず卒業」というものでした。 |
| 2007/10/31 「再び滝川高校での自殺について」 |
|
先日、神戸市にある滝川高校での自殺に関しての報道がありました。記事の見出しは、「<神戸いじめ自殺>高3さらに1人恐喝容疑で逮捕」というものでした。これはネットでの見出しですが、紙面でも同じような感じで掲載されていました。ここで、今月入り、滝川高校で起きた「いじめ」自殺に関する記事の見出しをあげてみます。
ここに挙げた記事は、Yahoo!ニュースの検索にかかったものです。紙面等で探せばもっとでてくると思います。 |
| 2007/10/19 「滝川高校だけの話として矮小化させてはいけない」 |
|
17日に神戸市教委に設けられている「神戸市いじめ防止対策推進委員会」が、私立滝川高校でネットいじめなどを原因で生徒が自殺し、同級生らが逮捕された事件などを受け、市立学校の保護者に対してネットいじめへの対策を盛り込んだ文書配布を決めたという記事が出ていました。メールやインターネット掲示板に悪口を書かれたり、個人情報を無断で掲載されるなどのネットいじめの現状を県の調査結果などから説明がなされ、予防と対応策として
などが示されれているそうです。
マス・メディアでの発表の情報なので、今、手元に具体的な資料がそろっていませんが、その報道を元にかんがえると、携帯電話の危険性やリスク回避の方法を家庭で話し合うといってもメディアリテラシーの専門的教育を受けていない親にとっては子供と何を話せばいいのか、どう話せばいいのかわかるはずもないと僕には思えます。僕は学校現場にいたときから、ヴァーチャル世界の危険性について学校教育でしっかりとメディアリテラシーを行うべきだと主張してきました。実際に耳を傾ける人は少なかったですが…。専門機関や学校でしっかりとメディアリテラシーに関しての授業を執り行うべきで、それは保護者に向けも同様に行い、その上で家庭での話し合いがあると思います。記事では「携帯電話」と限定された言葉が用いられていましたが、携帯電話だけでなく、パソコン(PC)でも同じことです。別に携帯電話に限定する必要はなく、むしろネット社会に対して警鐘を鳴らすべきだと僕は思います。 |
| 2007/09/30 「特待制度の決着?」 |
|
9月22日付け『毎日新聞』の記事には、「特待制度 条件付きで容認へ…各学年4人が軸 有識者会議」という見出しで記事がネット上に配信されていました。内容は検索していただければ分かると思いますが、一応ここにUSRを張っておきます。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070922-00000027-maip-spo 僕はここで注目すべきは今後、特待生をどのようにすべきかではなく、日本学生野球憲章第13条を破ったとのですから、そのルール違反に対して筋の通る処置を執るべきであって、今後のルール作りは二の次であると思うのです。 |
| 2007/08/19 「夏の甲子園」 |
|
すごく私的な事ですが、僕の家では『毎日新聞』をとっています。僕の知る情報は、まず『毎日新聞』からということになるのです。そこから関連する記事を探したり、情報を仕入れたりということになります。もちろん、教育現場の方からも情報はきますが…。 |
| 2007/07/30 「学校とは…」 |
|
前回、「教育に関するコメント」を書き込んだのは6月7日で、約2ヶ月弱ほど何も書き込まずにいました。更新もその間、ストップした状態で、ホームページを見ている人からは「更新してないけど、どうしたん?」と言われることもありました。 |
| 2007/06/07 「日和見的な教育の特集」 |
|
先ほど、「スーパーモーニング」という番組で教育現場の特集をしていました。録画することができませんでしたが、その内容は、保護者からどのような「いちゃもん」が寄せられ、それに対して教員がどれほど困惑・困ぱいしているか、というものでした。子供の成績が悪いから成績を改ざんしろ、いじめをでっち上げるようなこと、修学旅行についてくる保護者、夫婦喧嘩の仲裁を求められる、学校の桜の開花状況が悪い、子供がいじめられたから「誠意」をみせろ等々の報告が行われていました。 |
| 2007/05/30 「松岡利勝元農相自殺の報道」 |
|
このサイトは教育に関することを中心に情報の提示やコメントなどを掲載しています。政治的などろどろとした話をここでするつもりはありません。ですから、松岡元農相の自殺が緑資源機構の完成談合事件に関連し、もっと根の深い、表に名前を出せない人物たちが関わっていたのでは?というようなことをここでグタグタと論じようとは思いません。政界や経済界、その他の世界など我々が想像だにできないようなつながりや事があるのかもしれませんね。 今後、このようなことが起こらないよう文部科学省は全力で取り組んでまいります。
とおっしゃっています。また、伊吹文科大臣は2006年10月17日の「会見」で、福岡と北海道で起きたいじめによる自殺についてコメントされています。そのところを抜粋しますと、「従来いじめというのは、児童の間で行われ、その兆候を地域社会、家族、特に学校が、いち早く把握して、命を守ってあげるというのが本来の筋道だと思いますが、今回起こったことは、率直に言ってやや筋道から離れている、困ったことだと思います。特に北海道の事案では、いじめがあったことを訴えた手紙を残して自殺をしたということで、それまでにいじめの兆候が十分把握できなかったということも残念ですが、自殺の後、手紙があったという事実を、事実確認に時間がかかることは当然あると思いますが、いじめで困っている子どもの兆候を把握するべき学校、家庭、地域社会を束ねているといってもいい行政組織である教育委員会が長い間公表していなかったということは、非常に残念なことだと私は思います。福岡の事案は、私どもが聞いている範囲内では、児童によるいじめの引き金になったのが、児童を指導すべき教諭の言動であるとのことです。「やや軽率な」という報道がありましが、私は、教諭としての基本的な資質にやや問題があったのではと思います。…(中略)…北海道と福岡の教育委員会に対して、文部科学省として、本件についての調査を実施します。…(中略)…目的は3つありますが、1つめは、北海道と福岡での調査の結果を周知することです。2つめは、各都道府県、政令指定都市の教育委員会においても、今まで色々な事例があると思うので、困っている子どもの心のケアや子どものつらい立場を改善してあげることができた、というような事例を報告いただいて共有してもらうことです。3つめは、失敗は人間なのでありうることですが、大切なことは、失敗をしたことを隠さずに、みんなで知恵を絞って助け合って、一番困っている、いじめに遭っている子どもを助けてあげるんだという意識を共有してもらうことです。この3点についてお話をして、各地においてこういう残念なことを繰り返さないために、措置をできるだけ急ぐよう、指示をいたしました」そうです。 |
| 2007/05/11 「特待制度問題だけの問題?」 |
|
先月よりメディアに取り上げられている野球部の特待生制度がいつから騒がれ出したのか気になったのでYahoo!のニュース検索で調べてみました。便利な時代になったもので、以前なら縮刷版が出るのを待つか、人海戦術で大きな図書館にいって過去の新聞を軒並みあたるかどちらかでしたが、今では画面に向かいキーボードを叩くだけで調べることができるのです。どこまで信用できるかという議論はあると思いますが…。 |
☆過去ログ☆
| 2006年06月 | 2006年07月 | 2006年08月 | 2006年09月 | 2006年10月 | 2006年11月 | 2006年12月 |
| 2007年01月 | 2007年02月 | 2007年03月 | 2007年04月 |