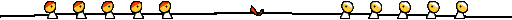教 育 コ ラ ム

| 2010/06/27「乞食支援」 |
|
ここで現政権である民主党について云々と政治批判しても仕方のない話であるし、そういう主張をする場ではないので、極力そのような批判は避けつつ話を進めていこう。 |
| 2010/06/14「教職生活って」 |
|
6月3日付けの教員免許更新制に関わる「お知らせ」において、「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策に関する検討状況について」と題された文章が掲示された。それを以下に示すことにしよう。 |
| 2010/05/31「当てモン授業」 |
|
昨日、5月30日はうちの子が通う学校で日曜参観があった。何故、日曜日に参観をしなくてはならないのかという議論はおいておくとして、日曜参観に参加しての感想をここで述べたい。 |
| 2010/05/07「倫理を教える」 |
|
いつだったか、京都大学で大麻所持等の事件が発生したことを受けて、大学の授業で「倫理」をとりいれるとの記事が出ていた。一時期は、中学生から大学生まで大麻を使用していた、所持していたとマス・メディアは情報の垂れ流しをしていた。大麻が何故使用することがいけないのかという議論をしていた新聞を見なかったが、とりあえず日本では大麻が法律によって禁止されている。だから大麻を使用するだけでなく、所持することもいけないのである。 |
| 2010/04/22「教員免許の剥奪・失効」 |
|
ある質問が寄せられて、以前より大阪府教育委員会にいくつか質問をしてきた。その質問を簡単にまとめるとどのようなことをしたら教員免許が剥奪又は失効になるのか、というものだった。ほとんどのいきさつについては、Q&Aに掲載しているので、それをご参照していただきたい。 |
| 2010/04/06「スーパーマリオ」 |
|
高校の授業料無償化や子ども手当が国会を通過して国民総乞食化計画が進行していますが、このことについては今までさんざん主張してきたことなので、今回はこの話題には触れません。「タダ」という言葉ほど後で高くつくものはないですからねえ。どこぞの何とか商法を政府が推進していると思った方が無難かもしれませんね。
先日、うちに子供が3人遊びに来ました。うちの子の同級生で、うちでゲームをするということで集まったそうです。そして、4人がWiiのゲームをなにやら始めて、これはどうの、こうの、と叫びあっていました。その姿を見ていて、僕は4人にWiiのスーパーマリオゲームをしてみてはどうかと提案しました。すると4人は「いいなあー」「しよう!!」と言い合ってそれぞれのマイリモコンを持って始めました。さて、8歳の男の子が4人同時プレーできるゲームをするとどのような展開になるか予想がみなさんにはつきますか? |