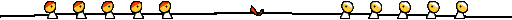教 育 コ ラ ム

| 2009/09/22「マイナーなのかそれとも無視か」 |
|
先日、Q&Aに教員免許の種類について説明をした。その際、教員免許には三種類あることを書いた。①普通免許状、②特別免許状、③臨時免許状の三つである。①については何ら説明をすることはないと思う。一般的に大学に通って教員免許に関する所要の単位を取得すればもらえる免許である。その取得の仕方の問題点などを言い出したらきりがないので、ここではこの辺で話を終えておく。②は特殊な経験や知識を持つ人に授けられるものであり、大阪府教委に尋ねると授与実績はないという。最後の③の臨時免許状というのがくせ者で、「教育職員検定に合格し、法が規定する欠格事由に該当しない者に対して、助教諭として授与される」免許状のことで、この免許状を大阪府教委は、平成21年度には20件の授与を行ったという。
発行数に関してはご丁寧に答えてくれているのであるが、こちらの問いである特定の学校の教員に日本の大学で教職単位を取得していない者に「特別な免許」を発行することに対しての質問には、「教育職員免許状は全て個人に対して授与するものであり、その授与に関連して申請者の勤務先などの個人情報に関わるご説明は差し控えさせていただきます」との答えであった。人の質問にはしっかりと答えるように指導しているはずの学校現場を管理する教育委員会の人間がまともに質問に対して回答できなのであるから…。 |
| 2009/09/09「より不安を煽ってみる」 |
|
「学力」の言葉が入ると話題になると思っているのか、「学力」テストの結果を大げさに不安を煽るように報道をする。序列をつけてより不安感や混乱を招くことができるので、結果公表云々に目を輝かせながら待ち構えているジャーナリストも存在している。保育所の話題になれば、待機児童がこれほどいるとかき立てて、代替案を載せることなく情報の垂れ流しをして無責任に不安を煽っているが、僕もこれに便乗してみようと思う。 |
| 2009/08/31「教育産業がにやり」 |
|
前回、このコラムで今回の総選挙でも教育産業がにやりとしているようなことについては次回と書いたので、出来レースではあるが、投開票が行われる今日にそのことについて書こうと思う。 |
| 2009/08/28「再び学力バカ」 |
|
先日来より今年4月に実施された学力テストの集計が発表された。国立教育政策研究所が発表したもので、インターネットが使用できる環境であれば結果等をみることができる。一応、ここでも結果のURLを提示しておこう。
今年、4月21日に実施された全国学力テストは |
| 2009/08/06「学力バカ」 |
|
PISSAの「学力」世界ランキングが話題となって以来なのか、客観的にバカが目立ってきたのを話題としたかったからなのか、ニュースの話題がなくなるととりあえず教育関連でバカを強調したいというマス・メディアの気まぐれなのか僕にはわからないが、ことあるごとに「学力」が話題となることが多い。このコラムでも「学力」に関することを書いてきて、その都度、「問題」がないことを主張してきた。今回は、大学教授の暇つぶしなのか「学力」と家庭の収入の相関関係が話題となっていた。 『読売新聞』では「親の収入高いほど子供は高学力、でも…」という見出しで、『毎日新聞』では「年収格差は子の学力格差」という見出しで記事となっていた。 その内容は、「文部科学省の委託を受けたお茶の水女子大の耳塚寛明教授らが分析した結果」によって「高所得ほど正答率も高い傾向がみられ、最も平均正答率が高かったのは、1200万円以上1500万円未満の世帯。200万円未満の世帯と比べると平均正答率に20ポイントの開きがあった」ことがわかったという。文科省はいくらで教授たちに委託したのかわからないが、とりあえず、予算が余っていたのか、暇つぶしをしたかったのかのんきな話である。 しかし、この結果を受け取る人間によってはのんきな話ではない。子供の成績が親の収入のセイにされるのであるから。親はたまったものじゃない。子は親の収入の低さを原因とし、親は子の努力や能力不足を原因とするのであろうか。そもそもいろいろな要因によって子供の才能は伸びると僕は思っている。遺伝的なものもあれば、後天的に才能を伸ばすこともあるし、環境因子によって子供の才能を伸ばすことができるだろう。 だいたい、冷静になって、「大学」「教授」「研究グループ」などと権威的な言葉に踊らされず考えてみると、高収入家庭の子の成績が「いい」傾向になるのは当たり前である。子供に対してつぎ込める余裕があるのだから。僕が塾業界にいたときも、金銭的に余裕のある家庭の子が通うのと、そうでない子では授業料へのつぎ込み方が大きく違っている。ここまで塾に金をつぎ込むことができるのかと感心するほどであった。 さらに、私立学校と公立学校に通わせることのできる環境も親の収入によって異なるのであるから、所謂「いい教育」を受けることができるのは、高収入の方がいいに決まっている。世の中にはバカ息子と言われる者もいるがそれでもいい環境になんとかおいてもらえるのは、収入にゆとりのある家庭だろう。こんなことを今更になって騒ぎ立てるような話ではないと僕は思う。あまり公になっていないが、両親がいる家庭と片親の家庭の「学力」格差も話題となる日は近いのではないだろうか。 なんでもかんでも「学力」に話題を引っかけて興味を引こうとするマス・メディアの在り方は問題であるが、そもそもこんなくだらない調査をしている者もたいがいだと思う。「学力」からもう少し身を引いてみては如何だろうか?「学力」以外に子供に対して目を向けることがあるし、その方が大切なのではないだろうかと僕は思う。 記事には「「本の読み聞かせ」や「ニュースを話題にする」は、親の所得に関係なく学力向上に一定の効果がみられた」ということが載せられていた。「学力バカ」の親はその日からでも「読み聞かせ」をして「ニュースを話題」とするのだろう。土足をはかしたままスーパーのカゴに子供を乗せている親よ、どうか読み聞かせやニュースの話題よりも食品をのせるところに土足のまま乗せている現状に目を向けてほしい。「学力」以前の問題がもっとあるのではないか? |
| 2009/07/17「資質向上のための利権=補助」 |
|
免許更新制に関しては、当研究所はくどいまでに問題があることを指摘してきましたし、反対もしてきました。僕の教員免許更新制体験談も掲載しました。
この補助金は、負担がのしかかる教員免許保有者ではなく、「質の高い免許状更新講習」を実施する大学側に支払われるものです。費用面での問題は実施される以前より指摘されてきました。いつから税金を投入する話が出てきたのか知りませんが、ようやく公に「補助金」という名目で税金を投入できるようになりました。このことで、どれほどの大学がいい思いをするのでしょうか。また、反対に泣きをみる大学も出てくるでしょう。 |
| 2009/07/10「何の研究開発?」 |
|
教育関係者以外の人間の耳にはあまり入ってこない言葉ですが、「研究開発学校制度」をご存じでしょうか?名前からして、何か教育に関することを研究して開発する学校なのかなあ、と思われるかもしれません。さらに「制度」という言葉がついているので、そこで何か感づかれた人もいるかもしれませんね。研究開発をする学校が制度として存在できるんですね。文科省は以下のように制度について説明しています。 恥ずかしながら僕はこのような制度があることを最近まで知りませんでした。公立学校の教諭でもなければなかなか知る機会はないと思います(いいわけのようですが…)。文科省では、文部省時代からこのような制度を展開させていました。その目的を端的に言えば、「学校における教育実践の中から提起されてくる教育上の課題や急激な社会の変化・発展に伴って生じた学校教育に対する多様な要請に対応するため」の制度です。この制度は、昭和51年ということですから、1976年から今年まで30年以上続いていることになります。30年以上も「教育上の課題や急激な社会の変化・発展に伴って生じた学校教育に対する多様な要請」の研究開発している学校がその都度、指定され解決のために取り組まれてきたのです。しかし、昨今マス・メディアが無責任な情報の垂れ流しと批判をする中で、教育に関する問題が提起されています。それらの問題についても、この制度で指定を受けた学校は研究開発をしているのでしょうか?研究開発しているわりには、問題解決がなかなかできていないように思えます。「ゆとり教育」の見直しなどを中心に教育業界は混乱・迷走しているような話も耳にします。このような混乱・迷走が起きないようにするために研究開発するための制度であると僕は思うのですが、その成果がなかなか現場では実感できないのは、僕の鈍感さのせいなのでしょうか。文科省は、研究開発の成果を以下のように記しています。 これまでの研究開発の成果は、教育課程の基準改訂に関する教育課程審議会の審議等の中で、具体的な実証的資料として生かされてきています。例えば、平成元年に告示された学習指導要領においては、小学校低学年の「生活科」の設置、中学校の選択履修の幅の拡大、高等学校の「課題研究」などの新しい科目の設定などの形で取り入れられましたし、平成14年4月から実施されている学習指導要領の「総合的な学習の時間」や「情報」「福祉」などの教科の創設に際しても、研究開発学校における実践が貴重な資料になりました。このほかにも、単位制高等学校や中等教育学校の制度化においても実証的資料を提供しました。更に平成20年3月に公示された小学校学習指導要領における外国語活動の新設にも、研究成果が活用されています。 この成果をいい意味で「生かされ」ていると言うのか、悪い意味で「生かされ」ているとみるかは「今」を生きているみなさんなら判断できると思います。さて、どうでしょう。 |