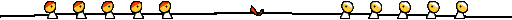教 育 コ ラ ム

| 2009/06/29「何を伝えるのか?」 |
|
今月のコラムは書かないでおこうと思っていたのですが、インターネットの記事の見出しがたまたま目に飛び込んできて、その内容を読むとこれは書かないと、と思うに至ってキーボードをたたいています。どんな内容の記事かというと、『京都新聞』が「訓告学生、また被害者を中傷 京教大集団暴行、より重く再処分へ」題うった記事です。いつものように以下の記事を掲載しておきます。
この記事を読んで浅薄な僕は疑問ばかりが出てきます。そもそも大学は何故処分をするのか?さらに厳しい処分以上に、「指導」とは具体的にはどのような内容のものなのか?この処分は一体誰のための処分なのか?と、いろいろ疑問が浮かびます。さらに、書き込んだ人間が特定されているのであれば、被害者なり警察はどのような対応をするのか、または対応をしないのかという点も気になります。野次馬的な興味ですが、マス・メディアに対してもこの情報を伝えることの意義は何なのか?何を伝えようとしているのか?僕にはわかりません。 |
| 2009/06/25「払えない者は去るべし」 |
|
たまたまインターネットでニュースをみていたら以下のような記事が出ていました。『産経新聞』のネット版の記事です。見出しは、「時効で“逃げ得”も 大阪府立高の授業料滞納4億円超す」です。
記事では、大阪は滞納者数も金額も多いように書かれていますが、数字から本当に大阪での滞納者が多いのか、金額も大きいのか僕にはわかりません。ただ一ついえることは、日本の場合、高校は義務教育下にありません。中学校までが義務教育です。高校は大学同様、行きたい者がお金を出して教育を受ける体制となっています。お金がないと日本の場合、高校さらには大学には通えないのです。奨学金制度を利用して通っている子がいますが、それは単なる借金であって、結局はお金を支払って通っています。 |
| 2009/06/14「京都教育大強姦事件から見えるもの」 |
|
今回は、京都教育大の学生が行った強姦事件についてコメントします。この事件には「教育問題」が含まれているので取り上げることにしました。そして、チョット事件の記憶が薄らぎつつある今、あえてこの事件について取り上げることにしました。
この事件は、①事件が発生した時期と社会的に話題となった時期に隔たりがあること、②大学側のとった行動に問題があったこと、③事件が明るみとなった後に別の形でその影響がでていることが特徴であると思います。 |
| 2009/06/06「教員免許更新制体験2」 |
|
前回の続きとなります。ようやく教員免許更新制の必修領域が終了しました。6月2日から始まって5日まで毎日18時から21時まで3時間の講習を受け、最終日に「試験」を受けてきました。初日のことについては前回に記載しましたので、ここでは二日目から最終日にかけての内容とそのまとめを書いていきます。 |
| 2009/06/03「教員免許更新制体験」 |
|
ようやくマス・メディアの新型風邪によるバカ騒ぎも引いてある程度落ち着きを見せきつつあります。関西では、集団感染の発祥のように言われている関西大倉でも1日から授業を再開しています。ただ、中傷誹謗が気になるというようなことをいっていましたが、人の噂が75日ももたない現代社会においてはあまり気にするようなことではないでしょう。 |
| 2009/05/18「冷静とは誰に?」 |
|
5月16日に「豚インフルエンザ」である「新型インフルエンザ」が国内で初めての感染が確認されたそうです。この「新型インフルエンザ」である「新型の風邪」が政府あげての「水際対策」をいとも簡単にくぐり抜けて、国内での感染となりました。成田空港で隔離されていた寝屋川の高校生たち、今回騒がれている関西大倉の生徒など、いったい誰が発生源であるのかという一種の犯人捜しがマス・メディアを中心に行われているようです。少なくとも茨木市にはメディアの人間が集まっていました。 |
| 2009/05/12「新型の風邪」 |
|
今月9日に大阪府寝屋川市にある府立高校生が、話題の新型インフルエンザに感染していることが判明したと厚生労働省が発表しました。このことについて、教育問題とずれることになるかもしれないが一言を付しておきたい思ってここにつづった次第です。 |
| 2009/04/30「正義を盾にした漢検いびり」 |
|
日本漢字能力検定協会に関する一連の騒動が下火になってきたが、あまのじゃくな僕はあえてここでコメントを書いてみます。教育と全く関係がないではないか、と言われそうですが、それは焦らずに最後まで文章をお読みくださいませ。 |
| 2009/04/09「教師の狭視」 |
|
前回コラムで僕が雇い止めになったことについて軽く触れました。そこで、今回は、その雇い止めに関連しつつ、僕が所属していたNPO法人が運営する「学校」のこと、そして、そこから派生してくる問題について論じます。 |
| 2009/04/03「同じ〈先生〉」 |
|
とうとう2009年度がはじまりました。僕も新しい環境で生活費を稼いでいます。この経済不況の最中、それなりに仕事ができていることに感謝しています。しかし、現状に於いては、雇い止めなどにより、仕事をなくしている人が多くいます。雇い主や企業の勝手な理屈によって、相手の生活を無視した雇い止めや解雇には腹立たしさを感じますが、個人レベルでは、いかんともしがたい状況、無力な自分にいらだちさえ覚えます。かくいう僕もつい先日、雇い止めにあいました。この件に関しましては、改めて記載しますが、ここでは先日公立学校で行われた新転任・就任式について論じたいと思います。 |