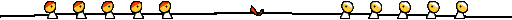教 育 コ ラ ム

| 2010/03/09「安心して勉学に打ち込める社会」 |
|
当研究所では高等学校の授業料無償化は愚策であると提言してきた。その理由が明確でないからである。文科省では、高校授業料無償化の理由づけをHPなどで公開している。2010年1月14・15日の説明会で開示された資料に掲載されている「趣旨」には「家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、公立高校の授業料を無償化するとともに高等学校等就学支援金を創設して、家庭の教育費負担を軽減する」とある。逆説的には、今まで授業料を支払うことによって、「安心して勉学に打ち込める社会」が創出されていなかったことになる。勉学に打ち込めるようにするか否かは、授業料の存在ではなく、本人の努力・姿勢であって、授業料のせいではない。自己の責任追求を放棄した社会らしい考え方だが、授業料を無償化したところで、「安心して勉学に打ち込める社会」が創出できるかは疑問である。 |
| 2010/02/24「愚策か良策か」 |
|
2月3日の『毎日新聞』に「府立高撤退ルール検討 私立と競争選別強化」と題された記事が掲載されていた。この記事にどれほどの人がどれほどの感想を持たれたのかは知るよしもないが、この記事を読んだときに「橋下さんは何を考えているのだろう」と素朴に考えてしまった。
法政大の教授が述べているように学校間の競争には「意味はない」と思う。「教育」を実施する「学校」は金儲けを主とした塾や予備校とは性質を異にしている。人が集まる塾がいい教育をしているとは必ずしも言えないだろう。もっと言ってしまえば、私立学校でも生徒が集まっているから「いい学校」とは言えない。大学進学をうたい文句にする学校は多い。特に私立学校はそれをやけに強調する。それは客集めのためである。目的もなく、とにかく大学に進学させるためだけの教育が展開されるのである。その結果は惨憺たるものであって、本当に「教育」を施す場所なのかと思えるぐらいである。偏差値を上げてくれる私立高校の順位付けまで雑誌などので紹介されているが、学校は偏差値を上げるためや大学に進学させるための機関ではないのである。しかし、常に「正しい」とされる「民意」からすると能力もないのに進級させてくれるような学校は「いい学校」となるのである。かくして無責任な社会の構成員が「学校」で養成されることになるのである。 |
| 2010/02/08「ツケを税金で払ってくれる国」 |
|
「子ども手当」について未だに議論がなされており、このコラムでも「子ども手当」については反対の立場で意見を述べてきた。この制度の是非についてはいろんな立場でいろいろ議論をしていけばいいと思っている。その「子ども手当」なるものの使い方について、2月に入って鳩山さんがある指示を出したという。その内容は、「子ども手当」を学校給食費の滞納分に充当できるかということを検討しようというのである。
|
| 2010/01/25「祝私立学校専願率上昇」 |
|
私立学校の専願希望が7年ぶりに上昇したそうである。公立中学3年生の進路調査に於いて私立専願希望者が16.55%を占めたという。この数字を多いととらえるのか少ないととらえるのかは様々であろう。不景気と言いつつも全体の16.55%の生徒が私立学校に進学できるというのであるから。一クラスに約6名ほど私立学校に進学することになるのだろう。 |
| 2010/01/11「新年の挨拶がわりに」 |
|
2010年が始まった。別に不思議なことではなく、2009年が終わったから2010年となっただけのことである。2010年が始まったからといって特別なことが起きるわけではないが、年が明けたということで、一言、あけましておめでとうと言っておく。教育に関して言えば、2010年になったから云々ではなく、過去からの流れで教育に関する状況が刻一刻と変化してるところもある。それが、いいことなのか、悪いことなのかわからないが…。
果たして、この記事を読んでけしからんと単純に言えるだろうか?そもそもこのような事が何故、新聞に掲載されるようなことになったのか不思議である。新聞関係者の子が通っていたのか、誰かが垂れ込んだのか…。教育現場では、意図的に情報のタレコミが行われることがあるが、この場合はどうだったのか知るよしもない。 |