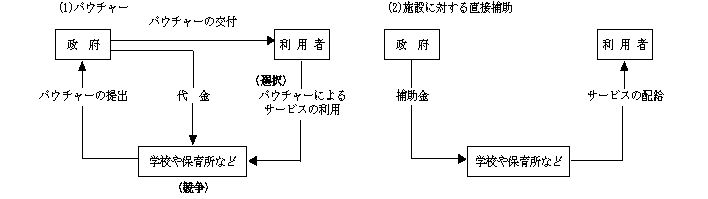Q1�F�w�Z�̐搶�ɂ͂��낢��Ȏ�ނ�����ƕ������̂ł����A�{���ɂ��낢�날���ł��傤���H
A1�F��ނƂ����ƕی��̐搶�Ƃ��̈�̐搶�Ƃ������ł��傤���A���Ԃ��̌ٗp�`�ԁ@�̂��Ƃ��ȁB���t�ƈ���Ɍ����Ă��A�傫����ʂ���3��ނ̋��t�����܂��B��́A�݂Ȃ��C���[�W���������w�Z�ɂ��āA���k�̖ʓ|����ƁA�N���u�Ȃǖʓ|�݂�搶�ł��ˁB����͐�C�u�t���C���@�ȂǂƂ�����l�ł��B�����A��C���@�̌_��Ј��o�[�W�����ŁA�d���̓��e�͓����Ȃ���1�N�Ԃ̊��Ԍ���̋����ł��i���������߂ɗ}�����Ă�������܂��j�B�Ōオ�A���u�t�Ƃ������̂ŁA�����Ă���1�N�_��ŁA�S���̎��ƈȊO�͎��R�ł��B�ł�����A�����̎��Ƃ��ς܂�����A���̌�A�w�Z�Ɏc��`���͂���܂���B�����܂ł��A���Ƃ����S������Ƃ��������̎d���ł��B

Q2�F�w�Z�̑I�ѕ�
A2�F�w�Z�Ƃ����Ə������Ƃ���܂����A�����ł͎����̒����w�Z�ɂ��Č��������Ǝv���܂��B�w�Z�̃p���t�Ȃǂ��݂�Ƃ��̊w�Z���ǂ̂悤�ȋ�����j�ōs���Ă���̂��킩��Ǝv���܂��B�ł����A���ۂɂ͂ǂ��̊w�Z������I���e�ɂ͂���قǂ̍��͂Ȃ��A�J���L�������̈Ⴂ��i�w�̂��߂ɂǂ̂悤�Ȃ��Ƃ����Ă���̂��Ƃ������炢�ł��B�l�̂�����ɂ͑����̎����w�Z������܂������w����ۂɂ͂��̊w�Z�̕��l�⍂�Z�Ȃ璆�w�Z�̒S�C�̑E�߂Ȃ�Ă����̂������āA������x�w�Z�����肵�܂��B�ł����A�w�Z�̑I�ѕ����`���b�g��������_�Ō��Ă݂Ă��������B�ǂ̂悤�ȂƂ�������邩�Ƃ����ƁA��ɂ������܂����悤�ɋ����ɂ͑傴���ς�3��ނ̌ٗp�`�Ԃ�����܂��B��C���@�ȊO�́A�Љ��ʂŌ����u�p�[�g�E�A���o�C�g�v�Ƃ�������ł��B���t������Ă���l�ɂ͂��̕\���ɕ�����o����l�����邩������܂��A�Љ�I�ɂ͂����Ȃ�ł��B�l���g������Ȃǂŏ��ނ�\������Ƃ��ɂ͌��ǃp�[�g�E�A���o�C�g�Ƃ����`�Ő\���������܂�������B�b��߂��܂��B�w�Z�ɐ�C���@�ɑ��āA�����u�t���ǂ�قǐ�߂Ă���̂��A���ׂĂ݂Ă��������B�����u�t�͂����Ƃ������i��肪���������Ƃ��Ȃǁj�ɂ͎���ȒP�ɐ��鑶�݂ł��B��E���u�t�̑����w�Z�͋�����e�Ƃ��Ă͎����Ⴂ�ƌ����܂��B�w�Z�Ƃ́A�����Ƃ��Љ�I��i����@������s���Ƃ���ł���ɂ�������炸�A��Ȏq��������₷���A�����A�Ƃ����`�Ōق��Ă��鋳���̑����Ƃ���ň��S���ėa���邱�Ƃ��ł���ł��傤���B���łɒʂ��Ă���̂ł���Έ�x�q������̊w�Z�ɂ��Ē��ׂĂ݂Ă��������B���Ԃ��킩��Ǝv���܂��B�܂Ƃ߂Ƃ��ẮA��E���u�t�̑����w�Z�͂��܂肢�����łȂ��Ƃ������Ƃł��B

Q3�F���Z�Љ�Ȃ̕K�C�Ȗڂ��ĂȂɁH
A3�F�����ł͎Љ�Ȃ̒n�����j�i�Ȍ�n���j�ɓI���i���Ă��b�����܂��B�w�K�w���v�̂ɂ́A���Z�ōŒ�����������Ȗڂ𗚏C���邱�ƁA�Ƃǂ̋��Ȃɂ�������Ă��܂��B���̎����ꂽ���̂����Ƃ̉ȖڂƂ��ĎĂ��Ȃ��Ƒ��Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��ł��ˁB���Z�̒n���ɂ́u���E�j�v�u���{�j�v�u�n���v�̎O���Ȃ�����܂��B�����āA���ꂼ��̋��Ȃɂ�A��B�ƕʂ�Ă��܂��B�Ⴆ�u���{�jA�v�u���{�jB�v�Ƃ���ɁB�g�p���鋳�ȏ���A��B�������Ă���̂Ŋm���߂Ă݂Ă͔@���ł��傤���H�n���̏ꍇ�A���E�j��A��B�ǂ���ł����܂�Ȃ��̂ŗ��C����K�v������܂��B����ɑ��āA�u���{�j�v�Ɓu�n���v�̑o�����ɗ��C����K�v���Ȃ��A�u���{�j�v���u�n���v���u���E�j�v���l��A��B�W�Ȃ����C����A���Ƃł���̂ł��B���͂����܂Ŏ��ԓI�ȗ]�T������̂��A�Ƃ����Ƃ���ł����A�������Z�Ȃǂł́u���C���Ă���v�Ƃ����悤�ɂ��Ď��Ƃ��Ȃ���Ă��Ȃ��ꍇ���悭����܂��B����́u�v�Ƃ������画�f�����ꍇ�A�����܂Ŏ肪���Ȃ�����Ƃ������Ƃł��傤�B�P���͂Ƃ������A���O�Ɩ{�����g�������Ă���Ƃ����Ƃ���ł��傤���B

Q4�F����ł�����o�E�`���[���x���ĂȂɁH
A4�F�o�E�`���[�ivoucher�j�Ƃ́A��ʓI�ɂ͕ۏؐl��ؕ[���������t�ł��B�ȒP�Ɍ����u�ؖ��v�ł��B�ǂ��炩�Ƃ����ƌo�ςŎg���錾�t�ł��B���̌��t���A����Ƃ�����ƌ��т��āu����o�E�`���[���x�v�Ƃ��u����o�E�`���[�V�X�e���v�Ȃǂ��낢�낢����悤�ɂȂ�܂����B����Ƀo�E�`���[�V�X�e��������c�_�͂���قǐ^�V�������̂ł͂���܂���B�����A����Đ���c�Ŏ��グ���Ă̂ŁA�b��ƂȂ��Ă���Ƃ��������ł��傤���H�{��ɓ���܂��傤�B����o�E�`���[�V�X�e���́A�w�Z����ɖړI�����肵���u�N�[�|���v���q����ی�҂Ɏx�����A�w�Z����̑I�����g�傳���邱�Ƃɂ���ċ����ɂ��w�Z����̎��S�̂������グ�悤�Ƃ������̂ł��B���w�⏕������̍l�����Ƃ�������������܂����A�ʂɌ����w�Z��I�����Ă����܂��܂���̂ŁA�P���ɂ����܂Ō����邩�͋^��ł��B�����܂ł��A�����w�Z�ɂ�����\�Z���̃N�[�|���s���āA�����ǂ���̊w�Z���I���ł���d�g�݂ł��B�����A�����̏ꍇ�͂��̗\�Z���邱�Ƃ�����̂ŁA���̕��͕ی�҂Ȃǂ̕��S�ƂȂ�܂��B�w�Z����ɑI���̎��R���������ꂽ�l���ł����A�����ɂ͂������̕ǂ�����悤�ł��B�����A���ӂ��Ă������������̂��A�I���́u���R�v���Ƃ��Ȃ������A�I�������u�ӔC�v�Ƃ����̂�����邱�Ƃɂ��Ȃ�܂��B�킩��₷���}���Q�l�ɓ���Ă����܂��ihttp://www5.cao.go.jp/keizai3/2001/0706seisakukoka8-q.html����Q�Ɓj�B
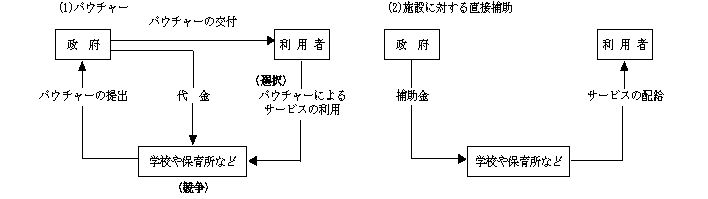

Q5�F�u�R���A���ۊw���v�ɂ��ĕ�����Ă��܂������A���̒��Ɂu�e��w�Z�Ƃ��ĔF�v�����Ƃ�����Ă��܂����B�u�e��w�Z�v���ĉ��ł����H
A5�F�w�Z����@��1���ɋK�肳��Ă���u�w�Z�v�ȊO���u�e��w�Z�v�ƌ����܂��B�w�Z����@��1���ŋK�肳��Ă���w�Z���u1���Z�v�Ƃ������܂��B�w�Z����@��1���ɂ́u���̖@���ŁA�w�Z�Ƃ́A���w�Z�A���w�Z�A�����w�Z�A��������w�Z�A��w�A�������w�Z�A�ӊw�Z�A�W�w�Z�A�{��w�Z�y�їc�t���Ƃ���v�Ɗw�Z���K�肵�Ă��܂��B�w�Z����@��83���ɂ́u�����Ɍf������̈ȊO�̂��̂ŁA�w�Z����ɗނ��鋳����s�����̂́A������e��w�Z�Ƃ���v�ƒ�`�Â��Ă��܂��B
�@�e��w�Z�Ƃ��Ă͗\���Z�⎩���Ԋw�Z���܂܂�邱�Ƃ������A�C���^�[�i�V���i���X�N�[���A���N�w�Z�Ȃǂ̖����w�Z�������͊e��w�Z�Ƃ��ĔF���Ă��܂��B�e��w�Z�ɂ��邱�Ƃɂ���āu�P���Z�v�������R�ȉȖڐݒ�A�J���L�������̍쐬���ł���̂ł����Ċe��w�Z�Ő\�����Ă���w�Z������悤�ł��B���R�w���ō��w���A���{�����_�w�Z�A������_�w�@�A���{���[�e���_�w�Z�Ȃǂ͂��̗�ł��B

Q6�F�X�[�p�[�T�C�G���X�n�C�X�N�[�����ĂȂɁH
A6�F�ŋ߁A���̌��t������ق�ƕ������Ƃ�����܂��B����́A���ȏȂ�2004�N�x����u�����n����Ɋւ��鋳��ے��̉��P�Ɏ����錤���J�����s���Ă���v�Ƃ��āA�u�X�[�p�[�T�C�G���X�n�C�X�N�[���v�i�Ȍ�ASSH�j�Ƃ��Ďw�肵���w�Z�̂��Ƃ������܂��BSSH�̖ړI�́A���ȏȂ̌��t�������Ɓu�����w�Z�y�ђ�����ы���Z�ɂ����闝�ȁE���w�ɏd�_��u������g���w���Ƃ̖��ڂȘA�g�̉��Ő��i���A�������ۓI�ȉȊw�Z�p�n�l�ނ̈琬�v���邱�Ƃ̂悤�ł��B
�@�ȒP�ɂ܂Ƃ߂�ƁA�����n���ꂪ�Ђǂ��Ƃ����b��M���ĕ��ȏȂ��\�Z�����A�e�w�Z�ŗ����n�̗D�G�Ȑ��k����Ă܂��傤�A�Ƃ����̂�SSH�ł��B���܂Ŋe�w�Z�ɂ��闝�n�R�[�X�Ƃ�������̂͂����������Ȃ̂��Ƃ����^�₪�킫�܂����A�u���ۓI�v�Ȑl�ވ琬�͓��ʂȂ̂ł��傤�B���̎�g�ɂ́u�w�K�w���v�̂ɂ��Ȃ�����ے��̕Ґ����{���\�v�Ƃ��Ă��܂��B�w�K�w���v�̂ɂ�鋳��ł́A�u���ۓI�ȉȊw�Z�p�n�l�ށv���琬�ł��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��ƐM�������ł��B
�@�����n�̐l�ވ琬�̂��߂ɂ͋��K�I�E�l�I�E���I�ɂƂĂ��D������Ƃ������ȏȂ̎p�����킩��܂��BSSH�Ɏw�肳���ƕ��ȏȂ��\�Z���z������A����w�Z�ł��Ɩ�2000���~�̗\�Z�����������ł��B�P���ɗ����n�琬�̂��߂̋���������Ƃ݂邩�A����Ƃ����������肽�����Ƃ݂邩�͋c�_�̂킩��ǂ���ł��B
�@���Q�l�܂łɁA2007�N4��1���t���̔��\�ł́A�V�K�w��Z���͌���16�Z�A����3�Z�A����3�Z�̌v22�Z�ł��B

Q7�F��Ƃ苳����Ă��������ȂɁH
A7�F1999�N�ɕ����Ȃƒ�������R�c��u��Ƃ�v�Əd�������w�K�w���v�̂��Ă��A���̌��ʁu��Ƃ苳��v���{�i�I�Ɏn�����܂����B�ړI�́A�u��Ƃ苳��v����Ă����ȑO�ɖ������Ă������l�����`��m���Ώd��`�����߂Ďq��������l��l�̔\�͂�L���Ă������Ƃ������̂ł����B
�@�������A1999�N�ȍ~�{�i�I�ɋ��猻��ɓ������ꂽ�u��Ƃ苳��v��10�N�Ƒ҂����ɘH���ύX�ƂȂ�܂����B��ɂ́A�����Ȋw�Ȃƃ��f�B�A���K�v�ȏ�Ɂu�w�͒ቺ�v�̌������u��Ƃ苳��v�ɂ��������̂悤�Ȃ��Ƃ���`���ꂽ���Ƃɂ���āA�u��Ƃ苳��v�������_�����ڂ���邱�ƂɂȂ�܂����B�u�w�͒ቺ�v�Ɋւ��ẮA�ʂ̍��ڂŘb�����܂����A�u����Ɋւ���R�����g�v�ł���M���ӌ����q�ׂĂ���̂ł����ł͏ڍׂ��Ȃ��܂��BOECD�ɂ���PISA�̒����E�����ňȑO�������ʂ��������Ă��邱�Ƃ����グ��ꂽ�̂ɒ[�����Ƃ����܂��B
�@�u��Ƃ苳��v�̍ő�̖��_�́A�u��Ƃ苳��v���Ȃ�Ȃ̂��H�u��Ƃ�v�̎w�����e�Ƃ́H���I�Ȏw���ɂ͖�肪����܂����A��̓I�Ȏw�j�������ꂸ����Ɋۓ����ɋ߂���Ԃɂ��ꂽ���Ƃɂ���āA����ɍ������������͔̂ۂ߂܂���B�����āA���{�⋳��ψ���A�w�Z����������Ɛ��������Ȃ������������ŁA�q�������ɂ́u��Ƃ苳��v���u�����Ȃ��Ă������v�Ƃ����l�����L�܂������Ƃł��B���錻��̋��t����́A�u��Ƃ苳��v������́u�����Ȃ��Ă������v�Ƃ������A���͋C���[�����A���Ƃǂ���ł͂Ȃ������Ƃ����܂��B
�@�����āA��l�Ɂu��Ƃ�v���Ȃ��̂ɁA�q���ɂ̂݁u��Ƃ�v�����߂Ă��ƒ�͉̏���ς�邱�ƂȂ��A�ނ���u�A�z�ɂȂ�v�Ƃ����\����y�j���Ɋw�K�m�ɒʂ킷�ƒ������A���̌��ʋ���Y�Ƃ����킷���ƂȂ�܂����B���ۂɁA�w�K�m�W�҂́u��Ƃ苳��v�ɂ���āu�w�͒ቺ�v�����������Ƃ��������̂Ȃ����Ƃ�K�v�ȏ�ɐ�`���āA�q�������Ɋl���ɗ��ł��܂��B
�K�肩�炢���Ɣƍ߂�Ƃ����ꍇ�́A�����Ƌ��̎����܂��͎�グ������̂ł��B��ɂ������������^�]�ł̌����Ɋւ��ẮA�����܂��͎�グ��������ꍇ������܂��ˁB